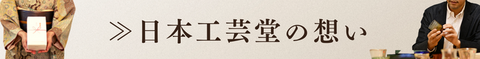錆びたらどうする?南部鉄器のお手入れ方法
南部鉄器については、「錆びてしまった」「お手入れの仕方が分からない」といったご相談をたくさんいただきます。わからないことがあれば、実際に生産者や職人さんに尋ね、生産現場で見て聞いたことを確かめながら、一つひとつ理解を深めてきました。
本記事では、そうして得た実体験と職人の知恵をもとに、使いはじめから日々のお手入れ、錆びたときの対処法まで、南部鉄器を長く安心して使い続けるための基本をまとめています。
目次
使いはじめのひと手間が使いやすさも決める使用後のお手入れで鉄器の寿命を延ばす
それでも南部鉄器が錆びてしまったら
南部鉄瓶のお手入れでやってはいけないこと
南部鉄器のお手入れは「毎日使う」が一番の方法
使いはじめのひと手間が使いやすさも決める
どんな調理器具でも、使いはじめにはしっかり洗ったり熱したり、はじめの儀式ともいえるお手入れが必要です。南部鉄器にも、購入して使い始める前に、ひと手間かけておきたいお手入れがあります。
鉄鍋は油ならしをする
フライパンやてんぷら鍋などの鉄鍋は、最初に「油ならし」をします。油ならしとは、鉄鍋の表面に油をなじませ、油の膜をつくるひと手間です。鉄鍋特有のにおいもこの作業を行うことで消えてしまいます。
<鉄鍋の油ならしの方法>
- 鍋の中のホコリやごみを水でしっかり洗い落とす。
- ペーパータオルなどで水分をふき取る
- 弱火にかけて水分をとばす
- 鍋底を覆うくらいの多めの油を入れて中火で熱する
- 野菜くずを入れて2~3分ほど、鍋肌全体に油がなじむように炒める
- 野菜くずを鍋から取り出たら、そのまま鍋を冷ます
油ならしをするときは、新しい油を使いましょう。
野菜くずを取り出した後は、ペーパータオルで軽く汚れをふき取ればOKですが、もし、汚れなどが気になるようであれば、軽く水洗いをしてもよいです。水洗いした場合は、洗った後、弱火~中火にかけ、水分をとばします。
鉄瓶はお湯でならす
お湯を沸かす鉄瓶も最初に「ならし」の作業を行います。
<鉄瓶のならしの方法>
- 鉄瓶全体を軽くすすぐ(たわしなどは使わない)
- 8分目まで水を入れて中火にかける
- 十分に沸騰したらお湯を捨てる
- この作業を2~3回繰り返す
最初に沸かしたお湯には色がついていることがありますが、何度かお湯を沸かすうちにこの色はなくなってきます。沸かしたお湯が無色透明になったら、ならし作業は完了です。
鉄瓶を火にかける際は中火にします。弱火で沸かすとお湯が濁ってしまうことがあります。
また、ならしは一度で完了ではありません。一定期間は毎日お湯を沸かす「ならし期間」を設けることも、鉄瓶を長持ちさせるポイント。毎日お湯を沸かすことで内側に被膜ができ、より錆びにくくなります。
急須はすすげばOK
南部鉄器には急須もあります。急須は内側がホーローなどで加工されているので、水と柔らかいスポンジを使い、2~3回洗えば使用可能です。
使用後のお手入れで鉄器の寿命を延ばす
最初のお手入れだけでなく、料理や湯沸かしで使用した後のお手入れは、南部鉄器にとってとても重要です。使ってすぐ、まだ鍋や鉄瓶が熱いうちにしっかりとお手入れしてあげましょう。
鉄鍋は使った後、しっかりお湯洗い
鉄鍋を使った後は、「しっかりとお湯で洗う」のがお手入れのポイントです。洗うときは金属たわしや洗剤などは使わず、亀の子たわしや竹のササラ、天然素材のブラシでお湯洗いします。
使用してすぐは鍋が熱いので注意が必要です。高温の鉄鍋をすぐに水に入れると破損の原因になります。お湯で洗うか、水で洗う場合は少し冷めてからにしましょう。
作った料理をそのまま入れておくのもNG。塩分の影響で鉄が錆びやすくなってしまいます。また、食材に含まれるタンニンと鉄分が反応し、料理が黒ずんでしまうことも。できあがったお料理はすぐにお皿に移して、鉄鍋は洗ってしまいましょう。
洗った鉄鍋は火にかけて水分を飛ばしておきましょう。乾燥した鍋には時々油を薄く塗っておくとより錆びにくくなります。
鉄瓶の基本は「使う分だけお湯を沸かす」こと
鉄瓶のお手入れは、お湯を沸かすために水を入れるところから始まっています。ポイントは「使う分だけお湯を沸かす」です。
鉄瓶を傷めるのはいつまでも中にお湯を残しておくこと。お湯が沸いたらすぐに中身をポットなどに移して中身を空にしましょう。そのまま蓋を外しておけば、余熱で鉄瓶の内部が乾燥できます。
もし水気が残ってしまっても、布巾などで拭きとってはいけません。鉄瓶を長持ちさせるのに必要な湯垢まで取り除いてしまうからです。水分が残っているようであれば、弱火で30秒ほど熱して乾燥させます。
蓋もあおむけにしておけば乾燥できます。表面の水分も乾いた布巾などでしっかり拭き取りましょう。

ポイントは「しっかり乾燥させる」
鉄鍋も鉄瓶も、使用後のお手入れのポイントは「しっかりと乾燥させる」ことです。使用後の余熱で乾燥させたり、洗った後に火にかけて完全に水分をとばすようにします。
ただし、空焚きのしすぎにも注意が必要です。必要以上に熱すると破損の原因になります。30秒ほど熱した後は、余熱を利用して乾燥させましょう。
それでも南部鉄器が錆びてしまったら
大切に使っていても、素材が鉄なので錆びてしまうこともあります。毎日使っていたのに内部が赤く錆びてきたという場合はどうしたらいいのでしょうか。
少しの錆は気にしなくてOK
実は、少しくらいの錆はそれほど気にする必要はありません。特に鉄瓶は使いはじめに赤く錆びたような斑点が出ることがあります。内部が赤く錆びたように見えても、沸かしたお湯が濁ったり、錆びた匂いがしなければ問題はありません。鉄錆は水に溶けだすことがないので、体に影響はないからです。気になるかもしれませんが、やすりや金たわしで無理にこすり落とすのは、水の中に錆の粉が入ってしまうので厳禁です。
なお、鉄瓶の中に付着する白い湯垢は水道水のカルシウムなどが付着したもので、錆止めの効果もあります。中が真っ白になるのは「鉄瓶が育った」証。削り落としたりせず、そのまま使いましょう。お湯がおいしくなる、とも言われています。

錆びが気になってきたら
それでも錆びが気になってきたら適切な方法で錆びを落とします。鉄鍋は天然素材のたわしでこすり落とした後、多めの油を熱して野菜くずを炒め、油をしっかりとなじませます。
鉄瓶は煎茶を煮出すのが効果的です。8分目まで水をいれ、お茶パックに茶さじ1杯ほどの煎茶を入れて、中火以下の火で30分ほど煮出します。途中、お湯が減ってきたら水を足し、空焚きにならないよう注意しましょう。2、3回繰り返してお茶を煮出すと錆びの色が気にならなくなります。
それでもダメならメンテナンスへ
それでも錆びが取れない、全体が錆びてしまったというときは、南部鉄器を購入したメーカーや職人さんに依頼してメンテナンスしてもらいましょう。錆のほかに異常がない場合は、高温で焼いて錆を落とす「焼抜き」という方法でメンテナンスができます。高温で焼くことで錆止めの役割を果たす酸化被膜を再生させます。
また、錆びて穴が空いてしまっても大丈夫。時間も費用も掛かりますが、小さな穴なら穴埋めもできます。大きな穴も「底入れ替え」で新しい底をつくれば、丈夫さも元通りです。
南部鉄瓶のお手入れでやってはいけないこと
南部鉄瓶を長くお使いいただくためには、「やってはいけないこと」を知っておくことが大切です。職人の手によって仕上げられた鉄瓶は、見た目の美しさだけでなく、内部の皮膜や熱の伝わり方など、すべてが計算された“道具”です。以下最後に、よくあるご質問をもとに、鉄瓶を傷めないための注意点をまとめました。
Q1:鉄瓶の内側をスポンジや金属タワシでこすってもいいですか?
A1:必ず避けてください。
鉄瓶の内側には、使ううちに「酸化皮膜」や「湯垢」が形成されます。この皮膜はサビを防ぎ、お湯をまろやかにしてくれる大切な役割を担っています。スポンジや金属タワシ、洗剤・研磨剤などでこすると、この皮膜を傷つけてしまい、錆びやすくなる原因となります。
内側は洗わず、お湯を捨てて軽くすすぐ程度で十分です。
Q2:使い終わった後、水を入れたまま放置しても大丈夫ですか?
A2:いいえ、水を残したままにするのは避けましょう。
鉄瓶に水を入れたまま放置すると、鉄が空気と反応してサビが発生します。使用後は必ずお湯を捨て、蓋を外して余熱で自然乾燥させてください。
湿気が残る場合は、弱火で数十秒ほど温めて水分を完全に飛ばすと安心です。このひと手間で、鉄瓶を長く健やかに保つことができます。
Q3:強火で急激に沸かしたり、熱いまま冷たい水をかけても大丈夫ですか?
A3:こちらも避けてください。
南部鉄瓶は中火以下の穏やかな火加減で、ゆっくりとお湯を沸かすのが基本です。強火で長時間加熱すると、金属が歪んだり、内側の仕上げが劣化する恐れがあります。
また、熱い状態から冷たい水を注ぐ「急冷」は、ヒビや破損の原因になります。使い終わった後は、自然に冷めるのを待ってから次の作業を行うようにしましょう。
南部鉄器のお手入れは「毎日使う」が一番の方法
鉄でつくられた南部鉄器を錆びさせずに保つのは、たしかに簡単なことではありません。けれども、使いはじめのひと手間を惜しまないこと、使ったあとはしっかり乾かすこと。 実は、それだけで十分に長く、美しく育てていくことができます。
そして何より大切なのは、「毎日使う」ことです。 鉄鍋なら油がなじみ、鉄瓶なら内側が自然に乾き、鉄そのものが強く、安定していきます。 大切だからと棚にしまい込むよりも、日々の暮らしの中で息づかせることが、いちばんのメンテナンスです。
南部鉄器は、使いながら育てていく道具。 日々の扱い方ひとつで、味わいも風合いも深まっていきます。 「こすらない」「濡らしたままにしない」「急激な温度変化を避ける」この3つの基本を守れば、鉄瓶は何十年も寄り添ってくれる相棒になります。
どうぞ、日々の湯気や音とともに、南部鉄器を“育てる時間”そのものをお楽しみください。
対象ブランド
| 【あわせて読みたい】 |
| > 「伝統工芸の魅力」記事一覧 |