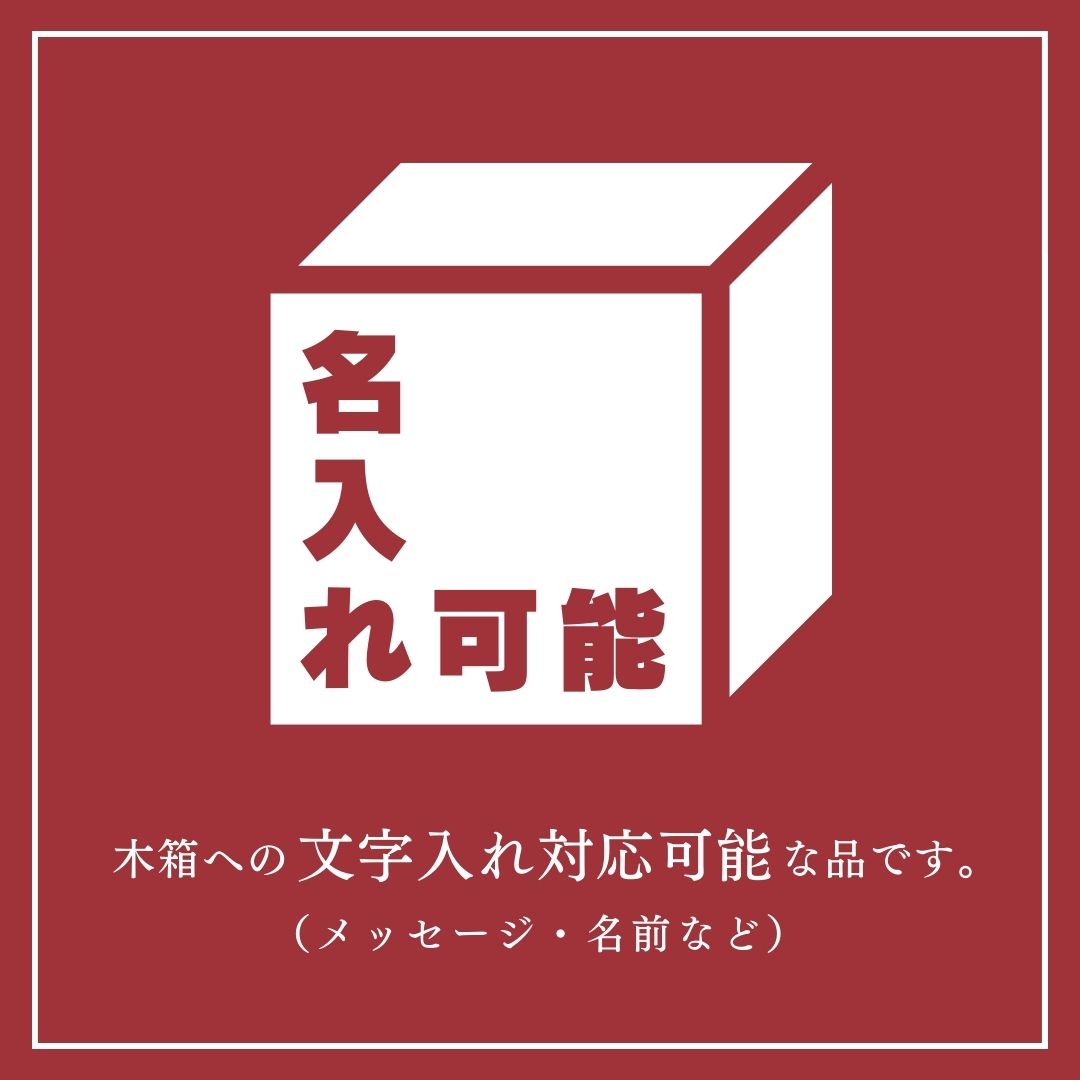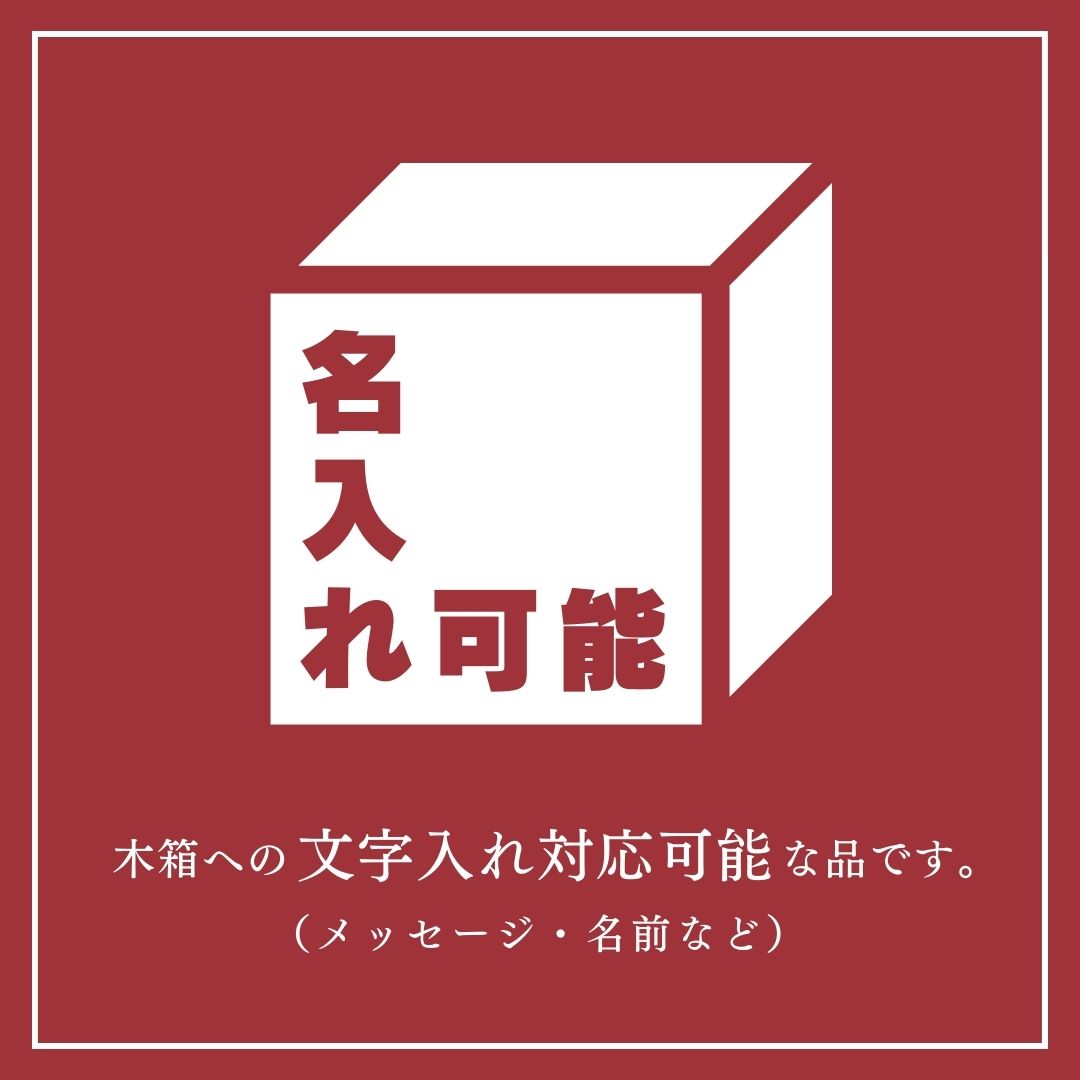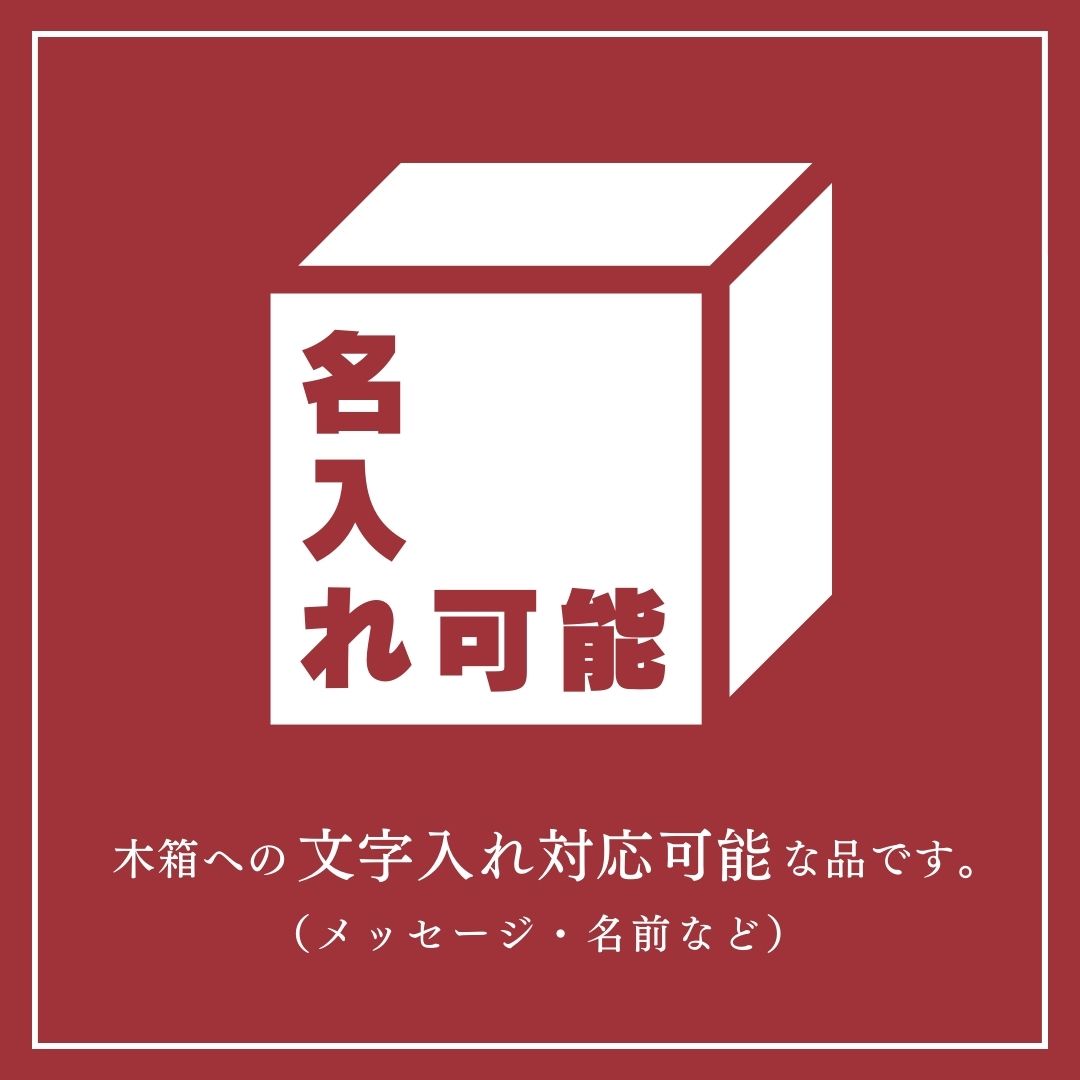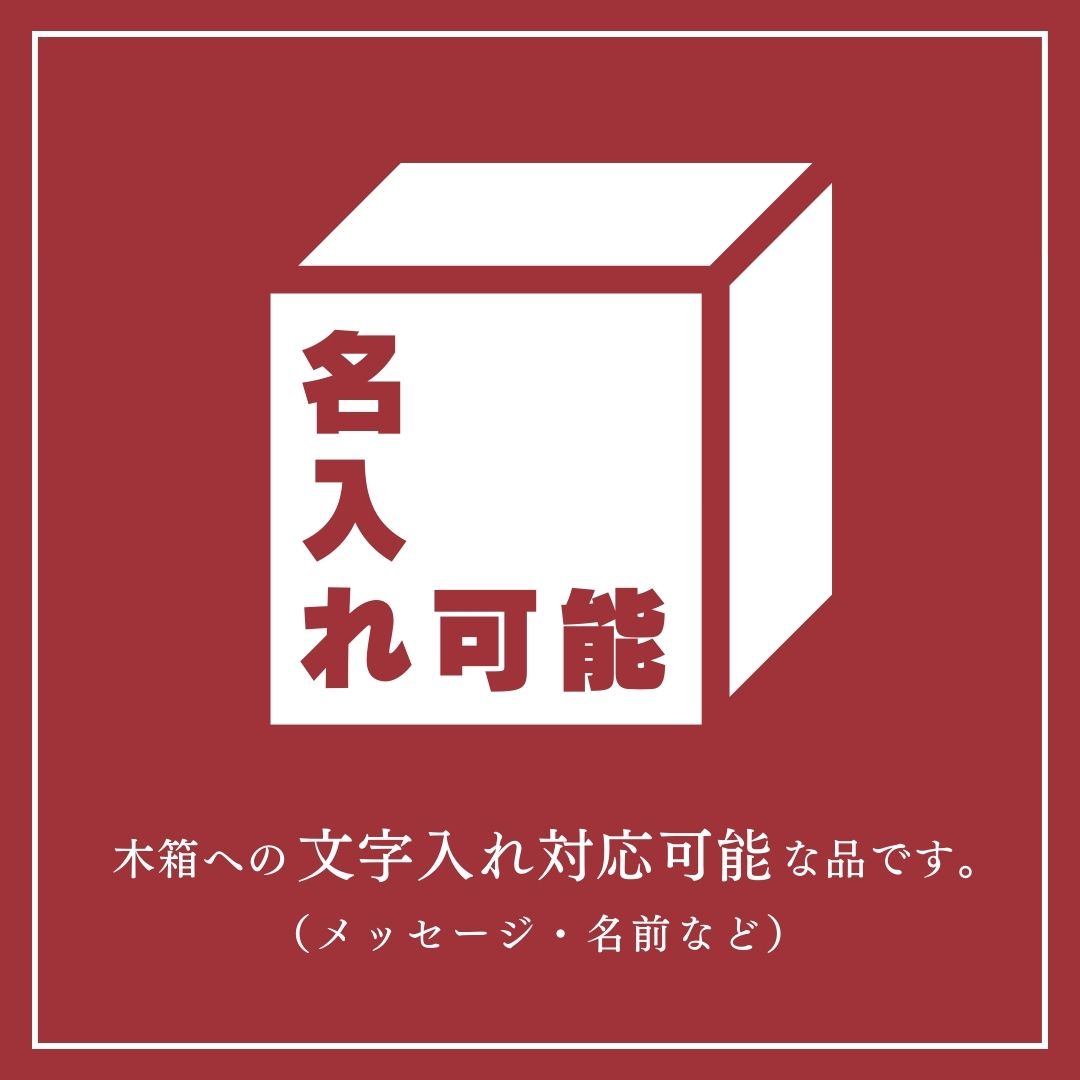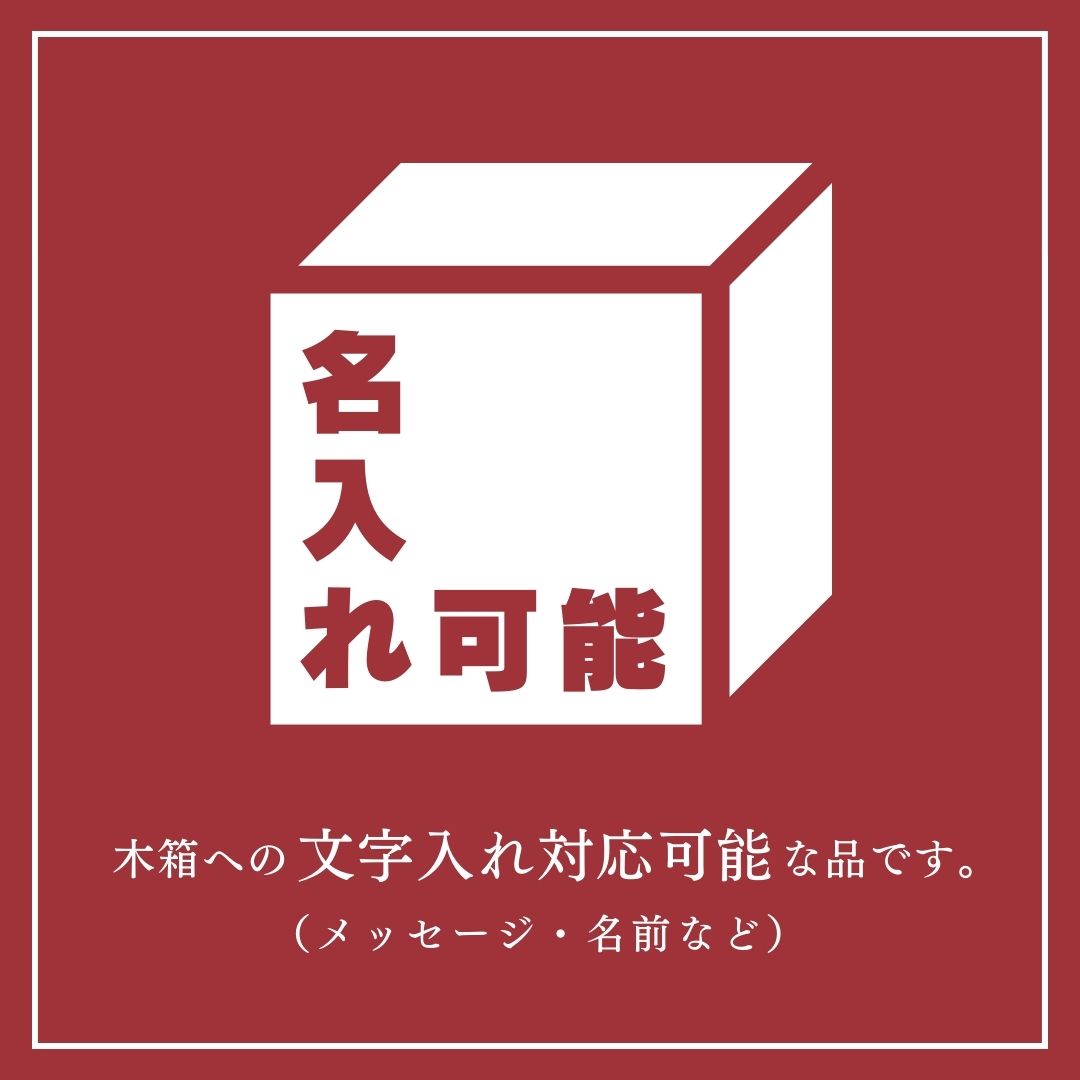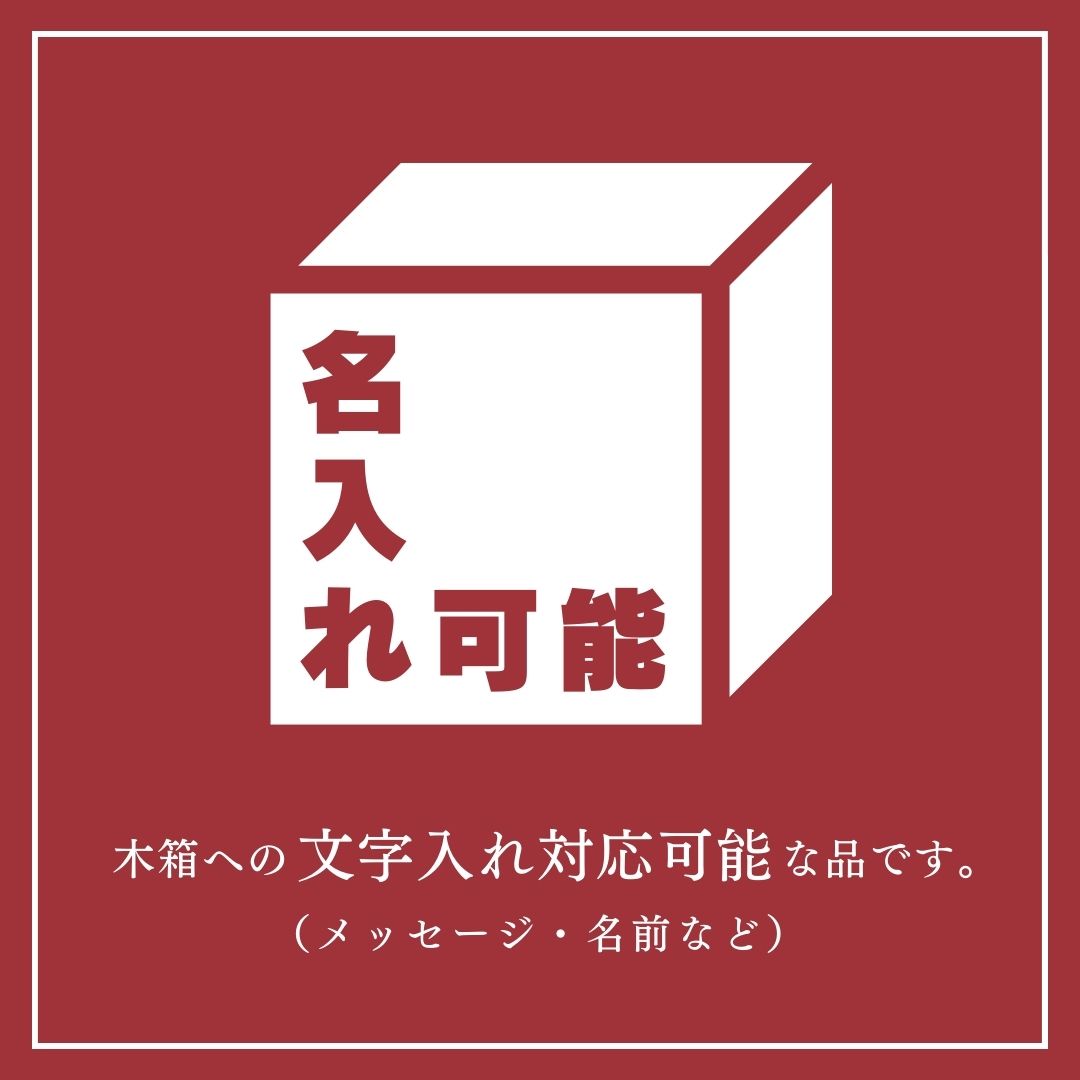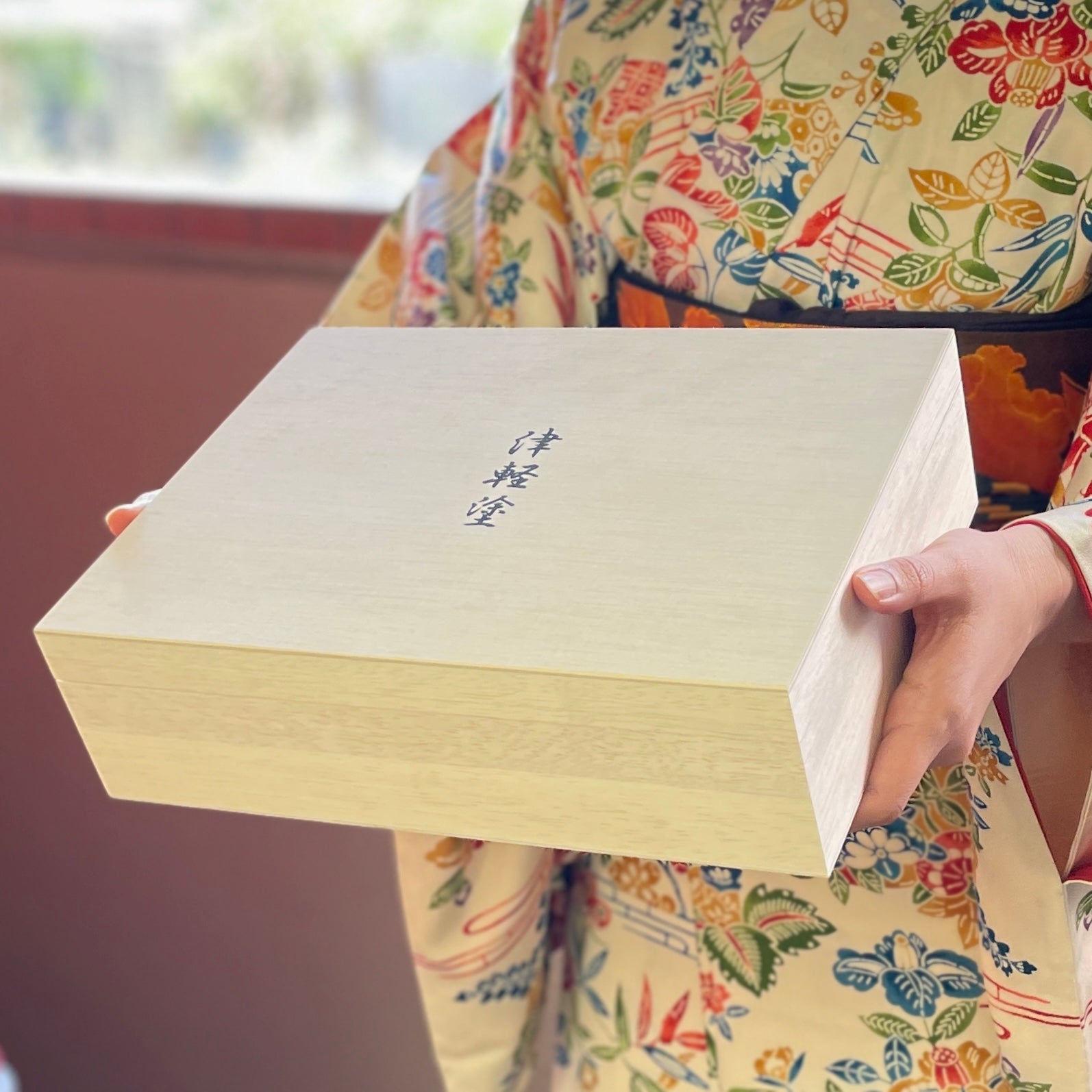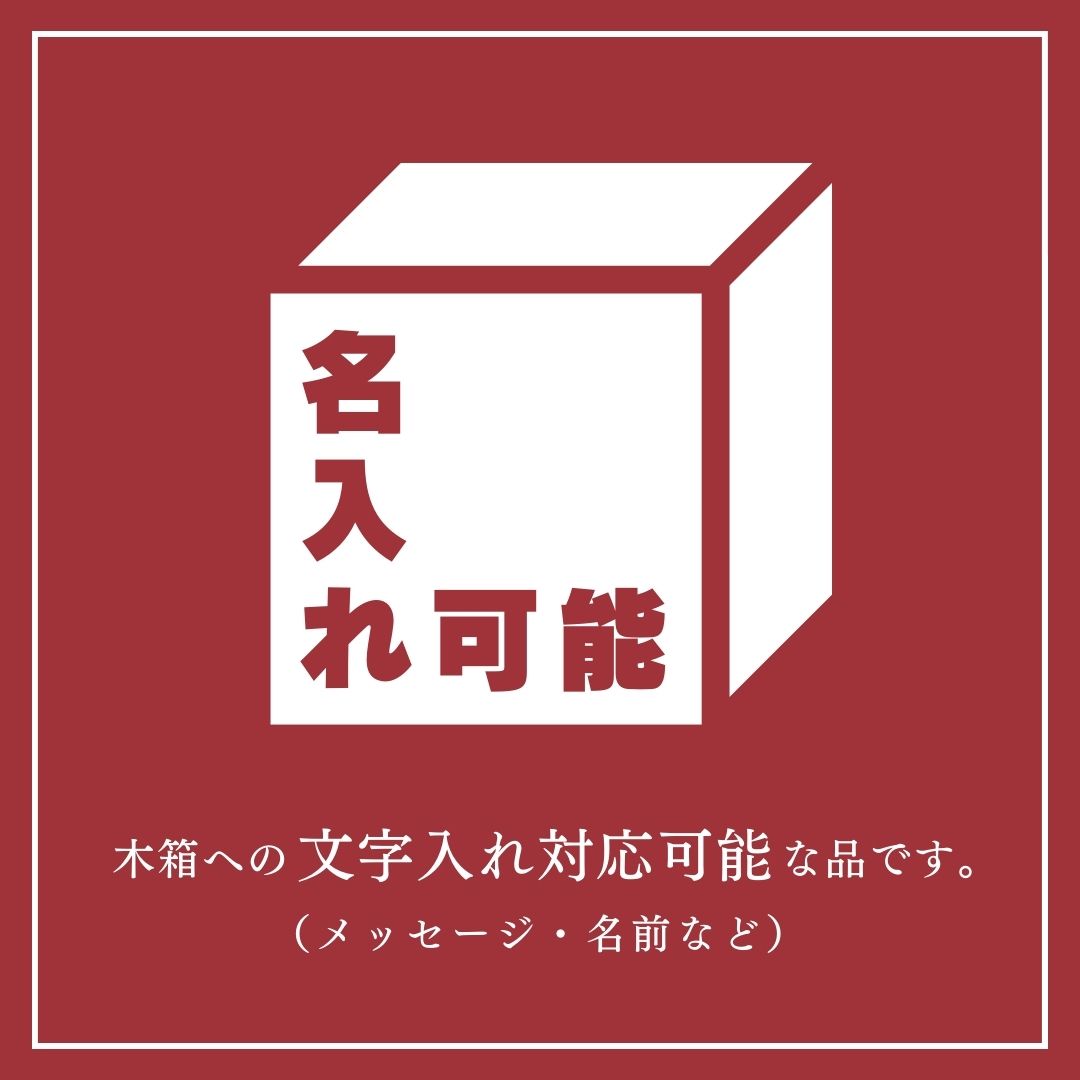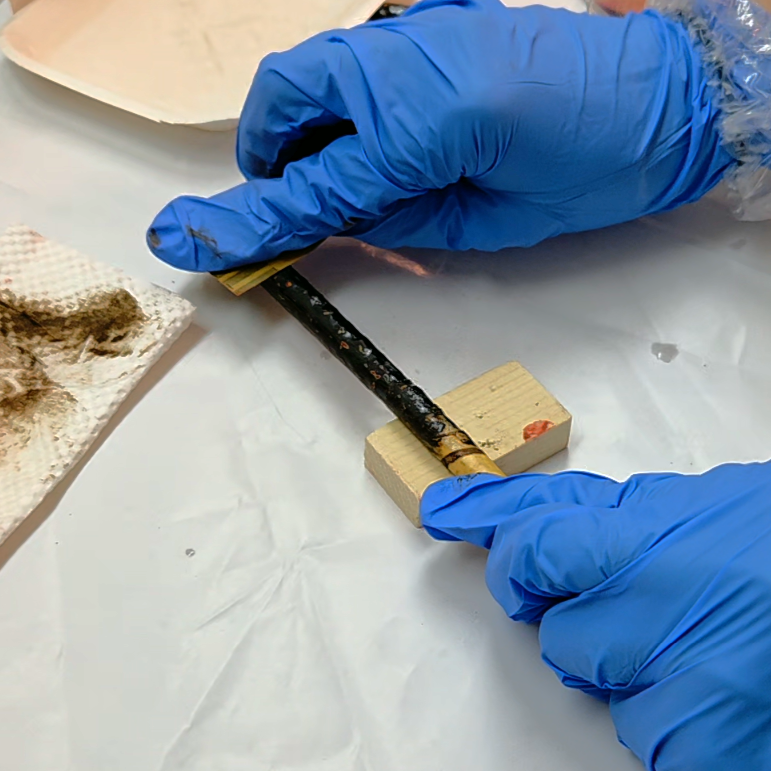フィルター
津軽塗 夫婦箸 | 唐塗 | 呂上 | イシオカ工芸
¥7,920
津軽塗 夫婦箸 | 唐塗 | 赤上 | イシオカ工芸
¥7,920
津軽塗 夫婦箸 | ななこ塗 黒上・赤上 | イシオカ工芸
¥14,520
津軽塗 | 箸 七々子塗 | 茜 | 小林漆器
¥6,380
津軽塗 | 箸 七々子塗 | 黒 | 小林漆器
¥6,380
津軽塗 | 夫婦箸 唐塗 | 呂・茜 | 小林漆器
¥6,930
津軽塗 | 夫婦箸 唐塗 | 藍・桃 | 小林漆器
¥8,030
津軽塗 | 夫婦箸 唐塗 | 梨黒 | 小林漆器
¥9,130
津軽塗 | 夫婦箸 七々子塗 | 緑・橙 | 小林漆器
¥12,760
津軽塗 | 夫婦箸 七々子塗 | 黒・茜 | 小林漆器
¥12,760
津軽塗 | 夫婦箸 七々子塗 | 藍・茜 | 小林漆器
¥12,760
津軽塗 | 夫婦箸 七々子塗 | 桜 | 小林漆器
¥16,060
津軽塗 | 夫婦箸 七々子塗 | 夢見月 螺鈿 | 小林漆器
¥27,060
津軽塗 | 夫婦箸・箸置セット 唐塗 | 呂・茜 | 小林漆器
¥11,660
津軽塗 | 夫婦箸・箸置セット 唐塗 | 藍・桃 | 小林漆器
¥12,760
津軽塗 | 夫婦箸・箸置セット 唐塗 | 梨黒 | 小林漆器
¥14,520
津軽塗 | 夫婦汁椀・箸セット 唐塗 | 呂・茜 | 小林漆器
¥37,400
津軽塗 | 夫婦汁椀・箸セット 唐塗 | 藍・桃 | 小林漆器
¥38,500
津軽塗 | 夫婦汁椀・箸セット 唐塗 | 梨黒 | 小林漆器
¥44,000
津軽塗 | 夫婦汁椀・箸セット 七々子塗 | 桜 | 小林漆器
¥68,200
体験キット | 津軽塗お箸研ぎ出しキット | 津軽燈LAB
¥19,800