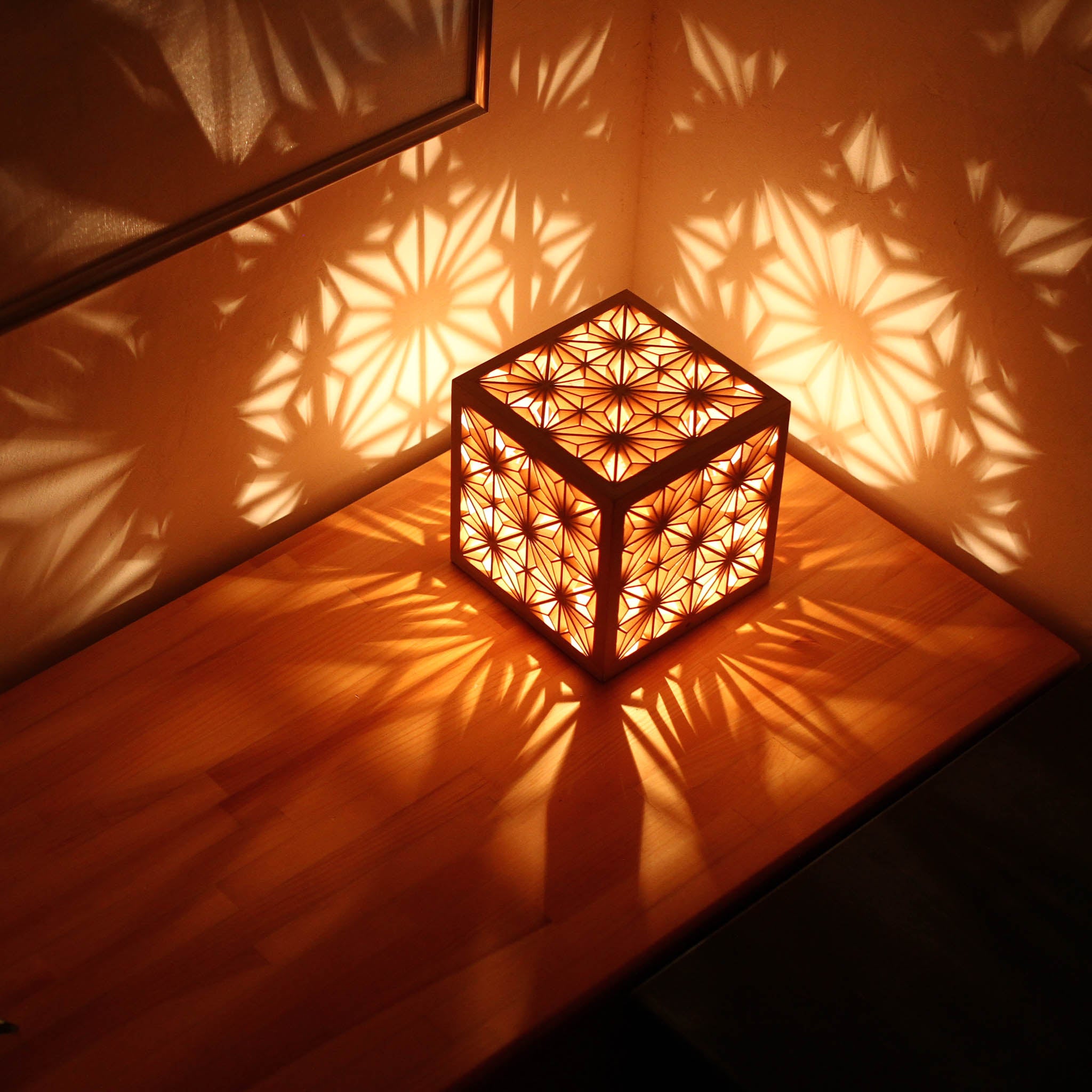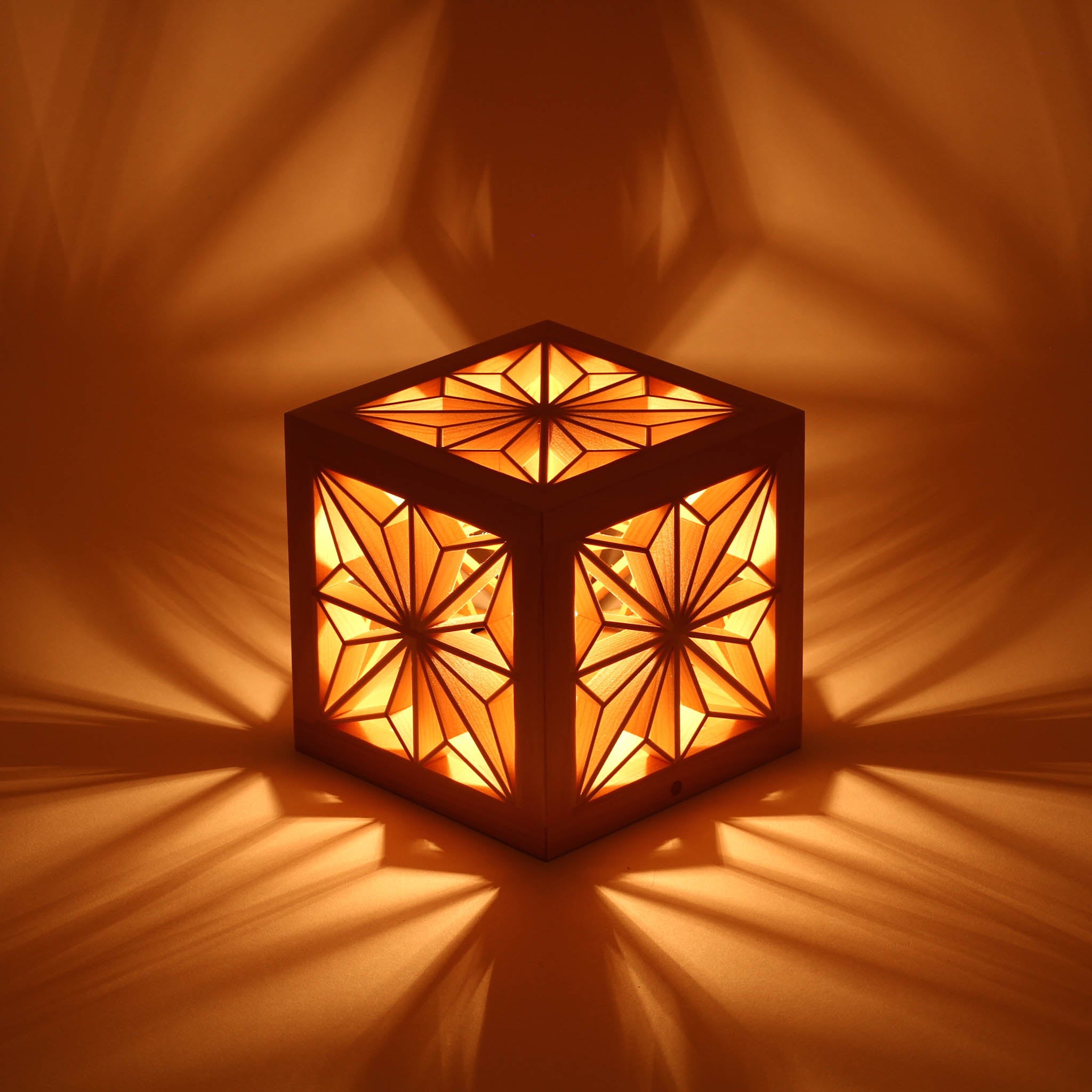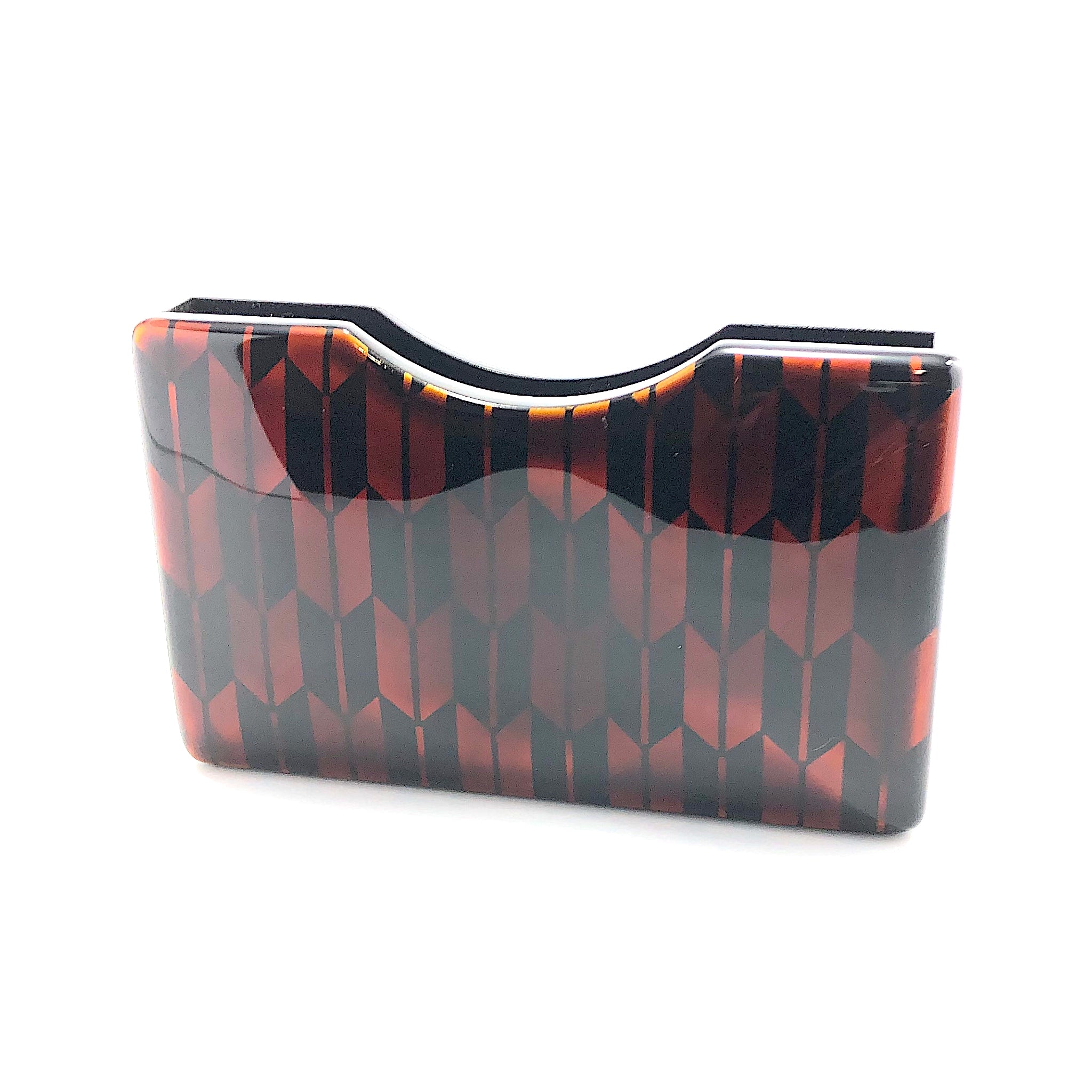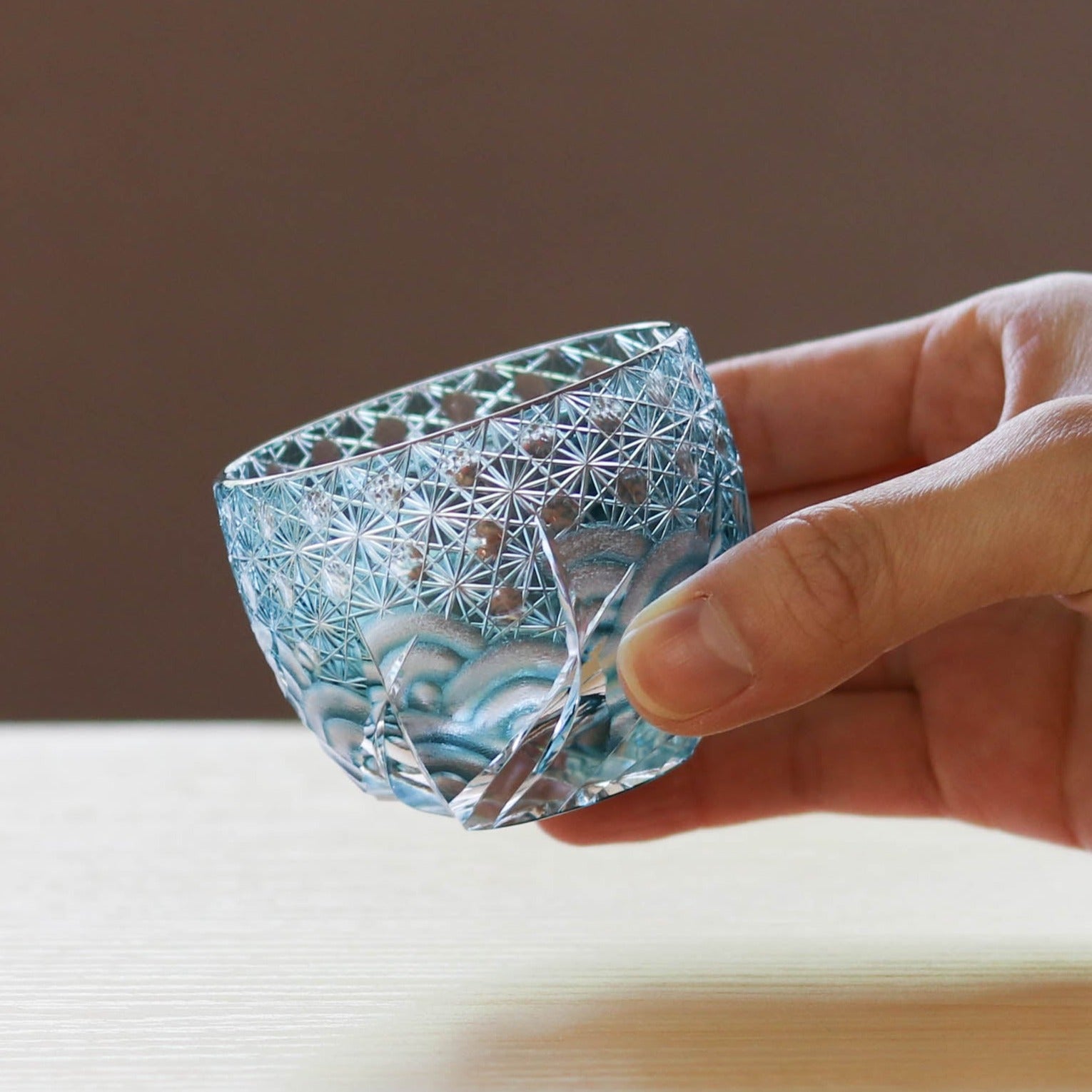フィルター
組子細工 テーブルランプ | 麻の葉キューブ D | 木のあかり
¥66,000
組子細工 テーブルランプ | 麻の葉キューブ M | 木のあかり
¥110,000
組子細工 テーブルランプ | 麻の葉キューブ S | 木のあかり
¥33,000
江戸硝子 そば猪口 | 大正浪漫 | 五客揃え | 廣田硝子
¥19,800
江戸硝子 グラス | 大正浪漫 冷茶 | 五客揃え | 廣田硝子
¥19,800
江戸硝子 一輪挿し | 大正浪漫 | 十草 | 廣田硝子
¥3,850
江戸硝子 一輪挿し | 大正浪漫 | 市松 | 廣田硝子
¥3,850
江戸硝子 一輪挿し | 大正浪漫 | 水玉 | 廣田硝子
¥3,850
江戸漆器 ピンバッチ | うるしピンズ | 螺鈿 折り鶴
¥4,950
江戸漆器 ピンバッチ | うるしピンズ | 螺鈿 桜
¥3,850
江戸漆器 ピンバッチ | うるしピンズ | 螺鈿 青海波
¥4,950
江戸漆器 ピンバッチ | うるしピンズ | 鯉
¥5,500
美濃焼 タンブラー | 市松カップ | シルバー
¥3,080
美濃焼 タンブラー | 市松カップ | ゴールド
¥3,080
美濃焼 タンブラー | 青海波カップ | ホワイト
¥3,080
美濃焼 タンブラー | 青海波カップ | ピンク
¥3,080
江戸切子 ぐい呑み | 漣 | エメラルドグリーン | 山田硝子
¥36,300