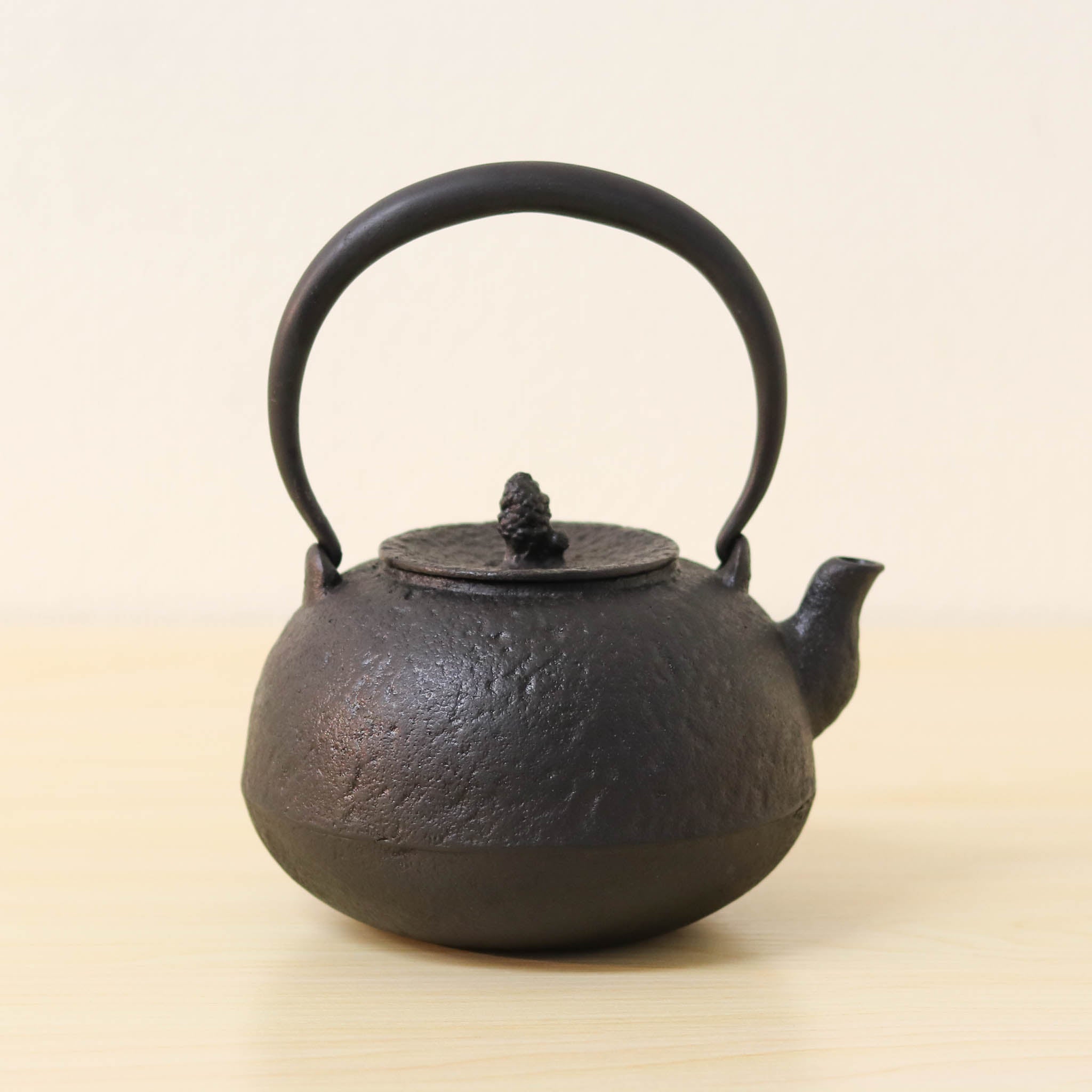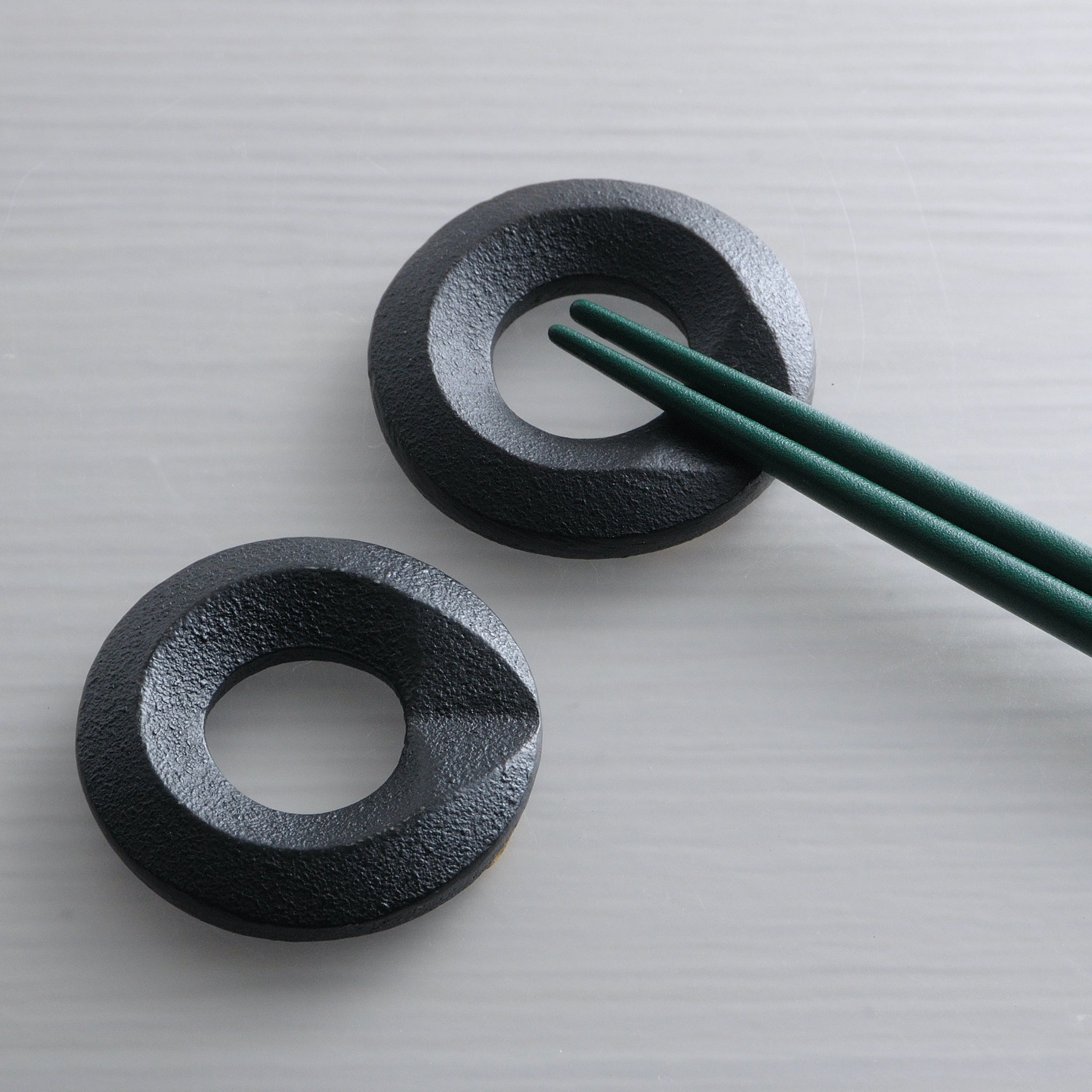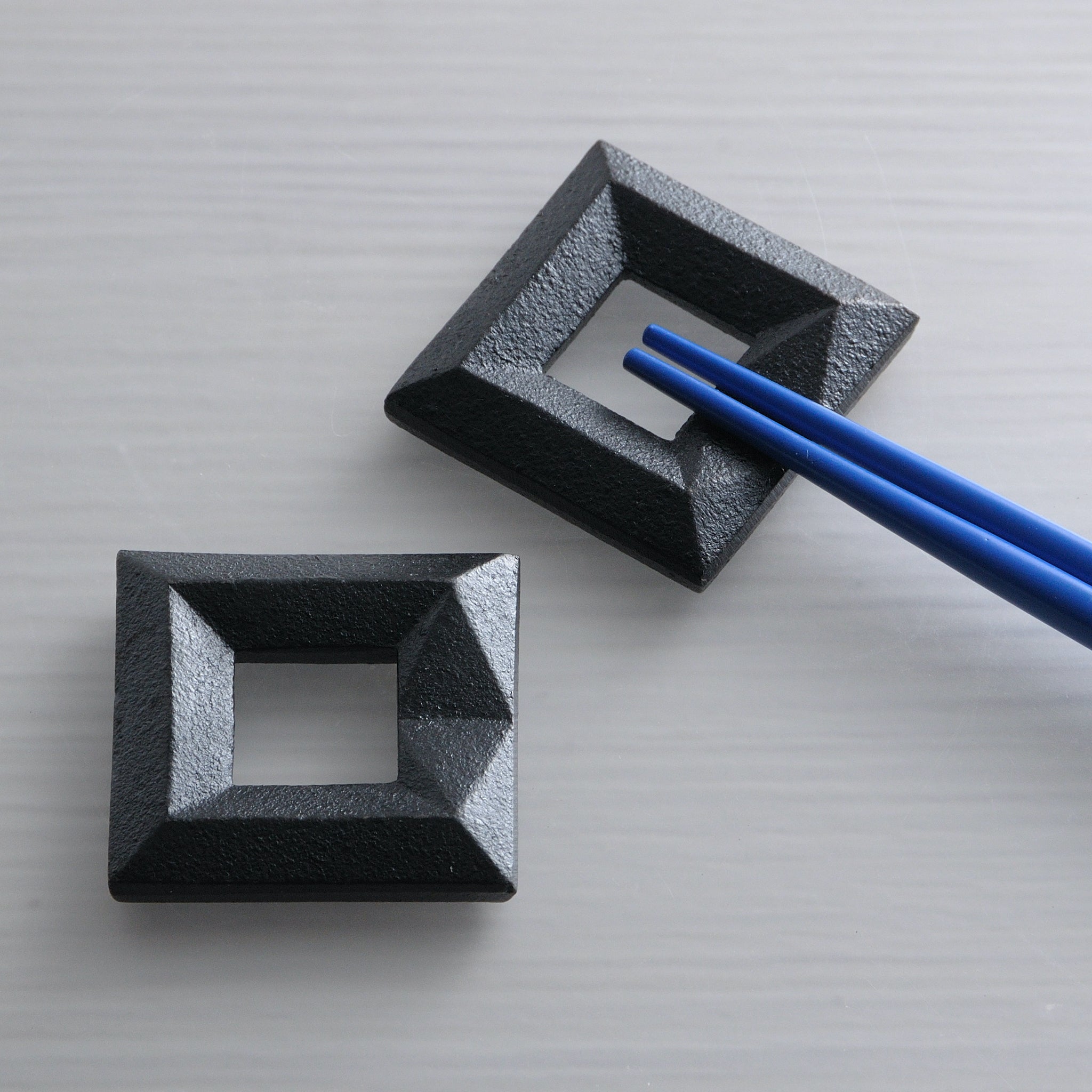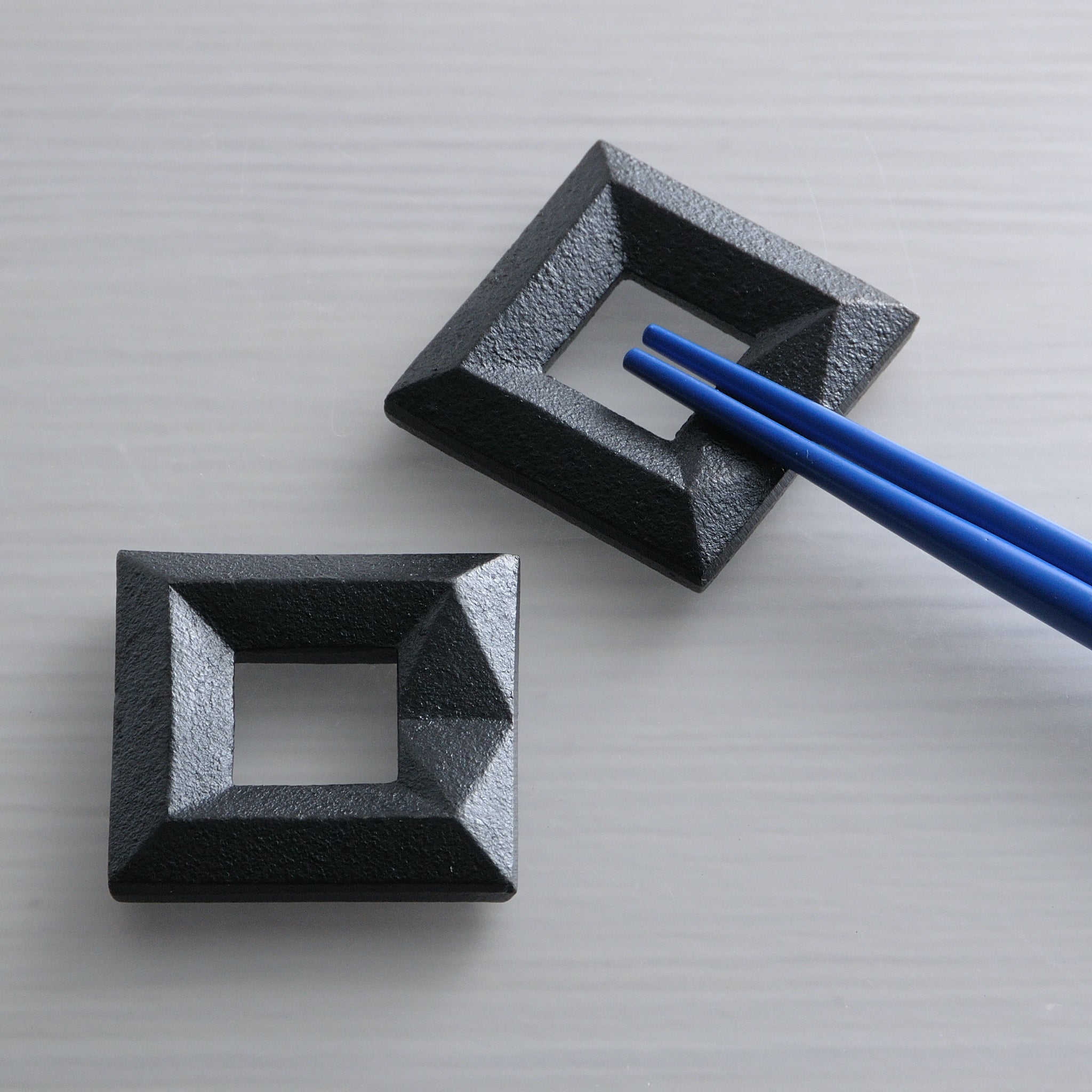フィルター
山形鋳物 鉄瓶 | なつめ | 6号 | あらい工房
¥33,000
山形鋳物 鉄瓶 | 尻張 | 8号 | あらい工房
¥30,800
山形鋳物 | 鉄鋳物フライパン | 蓋付き | あらい工房
¥18,700
山形鋳物 合せ香箱 | 源氏香 | L | 鋳心ノ工房
¥9,680
山形鋳物 鉄瓶 | 丸型 | 8号 | あらい工房
¥36,300
山形鋳物 鉄瓶 | 尻張 | 10号 | あらい工房
¥41,800
山形鋳物 鉄瓶 | 面取 | 10号 | あらい工房
¥55,000
山形鋳物 鉄瓶 | 平丸 七草 | 18号 | あらい工房
¥176,000
山形鋳物 合せ香箱 | 源氏香 | S | 鋳心ノ工房
¥8,030
山形鋳物 香箱 | 源氏香 | L | 鋳心ノ工房
¥8,250
山形鋳物 香箱 | 源氏香 | S | 鋳心ノ工房
¥7,150
山形鋳物 鍋敷き | 四葉 | 鋳心ノ工房
¥5,500
山形鋳物 鍋敷き | 五輪 | 鋳心ノ工房
¥5,500
山形鋳物 鉄瓶 | 平丸 無地 | 10号 | あらい工房
¥41,800
山形鋳物 鉄瓶 | 平丸 梅銀象嵌 | 10号 | あらい工房
¥275,000
山形鋳物 砂鉄製鉄瓶 | 平丸 無地 | 10号 | あらい工房
¥297,000
山形鋳物 鍋敷き | 笹車 | L | 鋳心ノ工房
¥4,400
山形鋳物 鍋敷き | UZUラウンド| 鋳心ノ工房
¥4,400
山形鋳物 鉄瓶 | 平丸 梅 | 10号 | あらい工房
¥44,000
山形鋳物 鉄瓶 | 平丸 老松 金彩 | 10号 | あらい工房
¥143,000
山形鋳物 砂鉄製鉄瓶 | 平丸 金彩富士馬 | 10号 | あらい工房
¥330,000