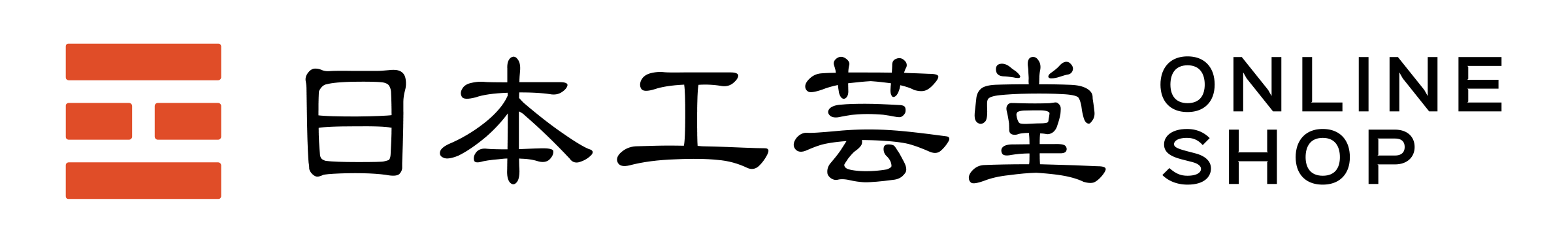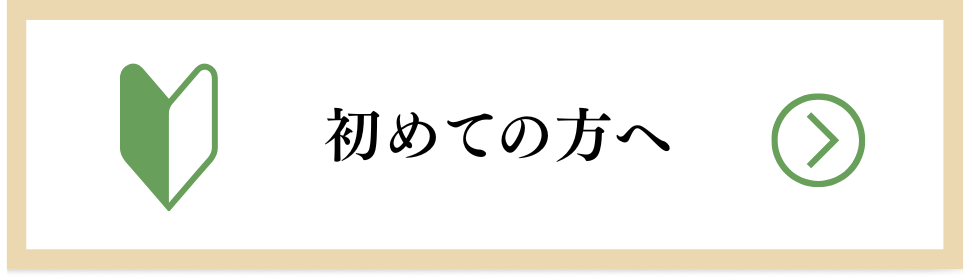海外でも人気の有田焼|贈り物に最適な理由と職人の技
日本で最初に作られた磁器「有田焼」は、繊細でありながら耐久性に優れ、華やかな絵付けが施されているのが特徴です。有田焼は、江戸時代には伊万里港から国内外に運ばれたため、「伊万里焼」とも呼ばれていました。
特に、柿右衛門(かきえもん)様式や金襴手(きんらんで)と呼ばれる華やかな絵付けが施された作品は、遠くヨーロッパにも輸出され、王侯貴族たちをも魅了し、やがてヨーロッパの陶磁器の歴史をも変えていくこととなります。そんな「有田焼」の歴史や魅力についてご紹介します。
有田焼の特徴
有田焼は、透明感のある輝くような白地に、美しい絵付けが施されていることが特徴。色絵の磁器には、さまざまな伝統的な様式があります。以下が代表的です。
■柿右衛門(かきえもん):赤・緑・黄色の顔料を使い、日本画のような柔らかい雰囲気で絵付けされた様式。繊細で優雅な表現。
■ 鍋島(なべしま):赤・黄・緑の三色の釉薬を使い、規則正しい模様で美しさを表現する格式ある様式。もともとは将軍家や大名家への献上品として作られていました。
■ 金襴手(きんらんで):赤や金をふんだんに使った華やかで豪華な絵付けが特徴。きらびやかで存在感のあるデザインが魅力。
これらの色絵磁器は、日本の伝統美を表現した芸術品として、江戸時代から現代にいたるまで世界中の人々に愛され続けています。
現在、有田焼には、以下のような表現技法が伝えられています。
- 白磁(はくじ): 美しい白地が特徴で、透明な釉薬(ゆうやく)を用いて焼成する。
- 陽刻(ようこく): 表面に凹凸をつけて、模様を浮かび上がらせる。
- 染付(そめつけ): 釉薬の下に呉須(ごす)という絵の具で絵付けする。呉須が藍色に発色する。
- 色絵(いろえ): 釉薬の上に、赤、緑、黄、紫、金、銀などで絵付けをする。
- 青磁(せいじ): 鉄分を含んだ釉薬を使って、青緑色に発色させる。
- 瑠璃釉(るりゆう): 透明な釉薬と呉須を混ぜることによって、瑠璃色に発色させる。
- 銹釉(さびゆう): 鉄分を含んだ釉薬で、赤茶色に発色させる。
- 辰砂(しんしゃ): 酸化銅を含む釉薬を、酸素が不足した状態で焼く(還元焼成)ことによって、赤色に発色させる。
なお、江戸時代に有田やその周辺で作られたやきものは、伊万里港から国内外へと運ばれていたため、「伊万里焼」「伊万里」などと呼ばれていました。
明治に入ってやきもの産地名で呼ぶようになったことから「有田焼」「伊万里焼」と区別されるようになりますが、結局、製法や原料などが同じであることから、「伊万里・有田焼」と統一して呼ぶようになりました。なお、特に江戸時代に作られたものを「古伊万里」ということもあります。
伝統あるブランドをご紹介すると、香蘭社が挙げられます。今からおよそ300年前、初代深川栄左衛門が有田で磁器の製造を始めたのが〈香蘭社〉の前進です。以来、その輝かしい伝統とともに、有田焼の伝統様式を一歩前進させたスタイルとして評価され、「香蘭社スタイル」と呼ばれ、広く親しまれています。
有田焼の歴史、ヨーロッパとの関係
1592年から1598年にかけて、豊臣秀吉が朝鮮へ出兵しました。文禄・慶長の役です。この時、朝鮮半島から陶工たちが肥前(ひぜん・現在の佐賀県)の大名鍋島直茂(なべしまなおしげ)によって連れてこられました。
1616年、この時の陶工の1人であった李参平(イサンピョン)が、現在の有田町で磁器の原料となる陶石を発見します。これによって、日本で初めて磁器が作られ「有田焼」の歴史が始まったといわれています。
初期のころは、「染付」だけの素朴なものでしたが、やがてさまざまな様式が生まれ、その美しさはヨーロッパの王侯貴族らをも魅了することとなります。
1650年代、「有田焼」はオランダの東インド会社を通じて、東南アジアやヨーロッパへもたらされました。当時のヨーロッパには磁器を作る技術はなく、中国や日本、朝鮮から輸入するしかありませんでした。
それだけにこうした東アジア産の美しい磁器を多数所有することは、富と権力のステータスシンボルとなり、王侯貴族らの間では磁器の収集が大流行します。さらに、17世紀後半にヨーロッパの王侯貴族の間で「柿右衛門」の人気が広まると、ヨーロッパではこれを模倣する窯も出てきました。ドイツのマイセン窯やフランスのシャンティイ窯がそれです。
また「金襴手」は、豪華絢爛な町人文化が花開いた元禄時代に誕生したもので、金や赤の絵の具を使って絵付けをする様式です。実用品としてはもちろん、装飾品としても欧州産のものと比べて遜色のないものだったので、こちらもヨーロッパなどで大変もてはやされ、盛んに模倣されました。
一方、国内では鍋島藩により「鍋島」様式が確立されました。1620年代後半から激しくなった内乱によって、中国大陸では明王朝が滅び、清が勃興します。鍋島藩では、明から輸入される陶磁器を将軍家への献上品としていたが、この影響を受け、陶磁器の輸入が困難になってしまいました。
そこで、有田焼の陶工のなかから、優れた技術を持つものを大川内山(おおかわちやま)に集め、献上品にふさわしい磁器の開発が始まりました。技術がもれることのないよう、陶工らを徹底して管理したことはよく知られています。
近代に入ってからも「有田焼」は、「ジャポニスム」などの日本ブームの中心的存在となりました。現在では、伝統的な技法を守られつつ新しいデザインや作品も生まれ、国内外に多くの愛好者がいます。2017年夏には、2020年の東京オリンピック・パラリンピック公式グッズとして、エンブレムの組市松紋を描いた「有田焼」の六寸皿が発売されました。
美術品としての有田焼
華やかな絵付けが特徴の有田焼は、実用品としてよりも美術品としての価値が高かったため、現在でも古いものが世界中の博物館や宮殿などにたくさん残されています。
特に、東インド会社を通じてヨーロッパへ運ばれた有田焼は、宮廷の装飾としても用いられていました。さらに、18世紀から19世紀にかけてイギリスで花開いた「アフタヌーンティー」の文化のもと、室内装飾のための調度や華やかなティーセットの需要が高まり、「柿右衛門」や「金襴手」は、その中心的存在としてもてはやされ、さらに多くの窯で模倣されるまでに至ります。
19世紀初頭のイギリス王ジョージⅣ世は、稀代の浪費家として知られているが、彼がこよなく愛したのが、「金襴手」でした。その影響を受けて、多くの窯が「金襴手」を模倣しています。
なかでも、ダービー窯には高い評価が下され、「クラウン」の称号も与えられました(以降「ロイヤル・クラウン・ダービー窯」と名称を変更)。やがてクラウンダービー窯は、マイセン窯とならんで日本風パターンの典型となりました。

一方、藩によって製法技術が秘匿された「鍋島」は、一般に流通するものではなかったため、その希少性もあって骨董的価値が非常に高いです。華やかな色絵の「色鍋島」、呉須の藍色が鮮やかな「鍋島染付」、美しく輝く青磁の「鍋島青磁」があります。また、「皿」が多いことも特徴で、サイズの種類もいくつかありますが、そのなかでも特に1尺の大皿は数も少なく一点物が多いです。
アリタセラで出会えるおしゃれな有田焼
アリタセラとは?
佐賀県有田町にある「アリタセラ」は、有田焼の魅力を体感できる複合施設です。約20,000坪の敷地に、陶磁器の専門店やギャラリー、カフェ、ホテルなどが集まっています。JR有田駅からタクシーで5分くらい。
この場所は、1975年(昭和50年)に「有田陶磁の里プラザ」として開設され、当時の有田焼の商社有志が集まり、世界最大規模の有田焼専門店街として誕生しました。 2018年(平成30年)には、「アリタセラ(Arita Será)」へと改称され、一般の人々も気軽に訪れて器を楽しめる場へと生まれ変わりました。
現在、アリタセラには老舗窯元から若手ブランドまでが出店しており、販売だけでなくギャラリーやカフェで器のある暮らしを体験できます。

アリタセラで出会える、おしゃれな有田焼ブランド
アリタセラには、伝統を受け継ぎながらも現代の暮らしに合う器を提案する魅力的なブランドが数多く並んでいます。その中から、当社でもお取引がある3ブランドをご紹介します。
賞美堂:1959年創業。先人たちが伝え守ってきた伝統と革新に溢れた有田焼の美を、現代の焼物に甦らせることを目指し、1990年にオリジナルブランド「其泉」を生み出す。
「時代をこえて美しく」を合言葉に、後世に伝えたい価値ある商品を生み出し続けています。
KIHARA:有田焼・波佐見焼の産地商社として、この400年の伝統技術と先人たちの想いを胸に、現代の生活に合わせた商品開発を行っています。
金照堂:有田の伝統技術を生かし、新しい生活シーンに調和するブランドを創り出し続けています。「麟 -Lin-」は2016年の有田焼創業400年事業を契機に誕生し、現在は金照堂の主力商品ブランドとなっています。 
参考:
- 有田観光協会ありたさんぽ
- 青山窯
- 日本のやきもの
- (財)伝統的工芸品産業振興協会監修『ポプラディア情報館 伝統工芸』ポプラ社 2006
- 『図説 英国ティーカップの歴史 紅茶でよみとくイギリス史』Cha Tea 紅茶教室 河出書房 2012
| 【あわせて読みたい】 |
| >「伝統工芸の魅力」記事一覧 |