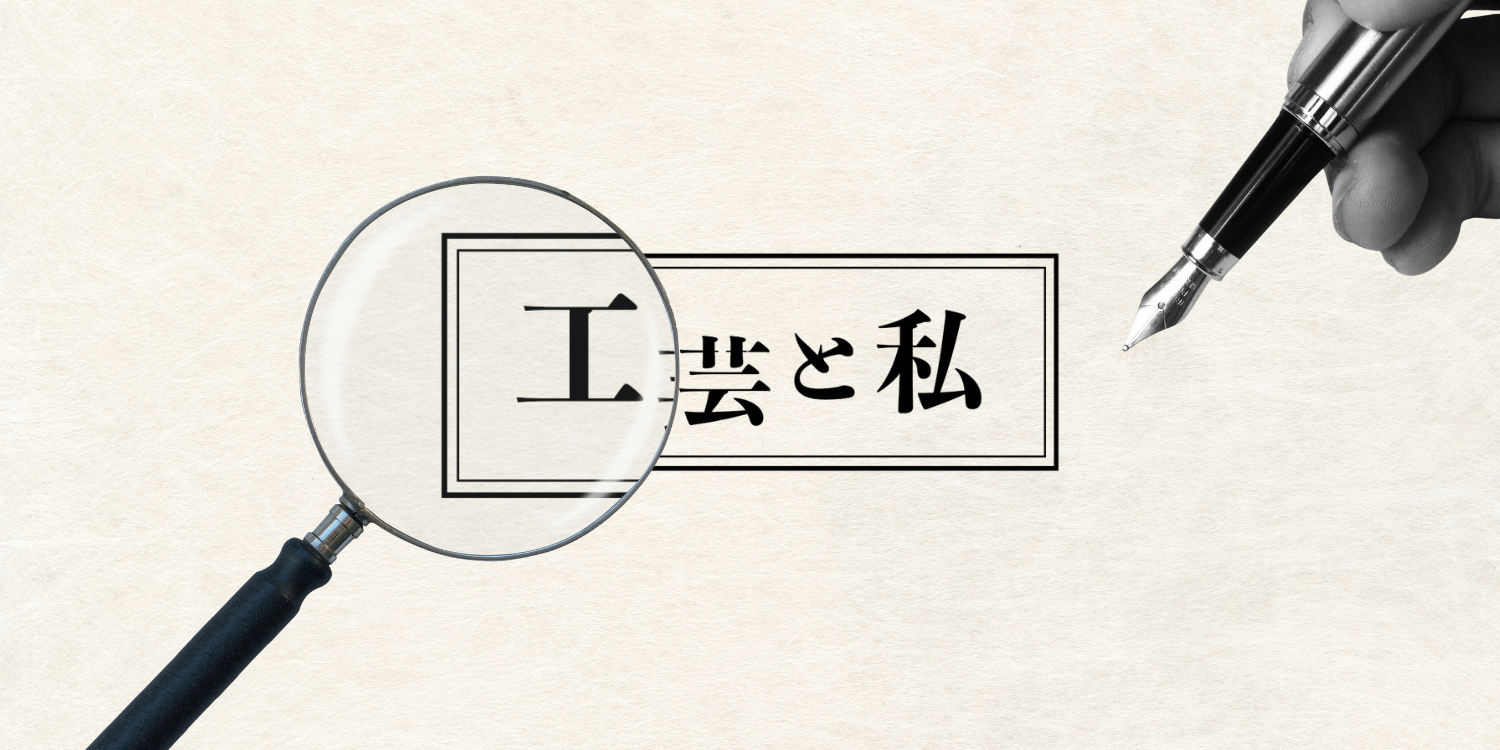記事: 【つくり手に聞く】自然のひかりを、切子に映して/青山 弥生(江戸切子職人)

【つくり手に聞く】自然のひかりを、切子に映して/青山 弥生(江戸切子職人)
夏のある土曜日の午前、静かな空間に差し込む自然光の中で、江戸切子伝統工芸士で、青山硝子工芸・青山弥生さんにインタビューを行いました。
その語り口は、まるで彼女の作品のよう。繊細で凛とした佇まいに、言葉のひとつひとつがガラスのカットのような緊張感をまとっていました。
本記事は、そのインタビューをもとに構成しています。江戸切子の技と感性に向き合うひとときが、読者の皆さまにとって、この伝統工芸を知る小さなきっかけとなれば嬉しく思います。文責:松澤斉之(日本工芸株式会社)
自らの手で、想いをかたちに─独立の背景

青山さんは、大学でインダストリアルデザインを学んだのち、「手でものをつくる仕事」に惹かれて伝統工芸の道へ。
実は学生時代から、彫刻や工芸など“手でつくる世界”への関心が強く、当初からそうした道に進みたかったといいます。ただ、就職を考えてインダストリアルデザインを選んだ経緯があり、同級生たちが企業でプロダクトデザイナーとしてキャリアを積んでいくなか、「やっぱり“つくること”そのものが好きだった」と、あらためて自身の原点に立ち返ったそうです。
「遠回りだったかもしれませんが、結果的に“好き”なものに戻ってこられてよかったです。やっぱり好きなことじゃないと続かないですしね」
そう語る表情には、静かな覚悟とものづくりへのまっすぐな想いがにじんでいました。
未経験ながら清水硝子の門を叩き、職人として一から技術を学びました。

長年にわたり制作に携わるなかで、カット技術を高めながらも「自分の作品をつくりたい」という気持ちが次第に強まり、2025年、自身のブランド「青山硝子工芸」を設立。作家として独立を果たします。
現在も清水硝子の工房の一部を間借りしながら、自身のブランドとして制作を行っています。「場所や道具を含めて、本当にありがたい環境に支えられています。独立はしましたが、ここまで続けてこられたのは、まわりの方々のおかげです」
自身の表現を追求しつつ、職人としての積み重ねを大切にするその姿勢に、青山さんならではの誠実さが滲んでいました。
糸の美しさを、カットに託す─《織々(おりおり)》という視点
細い糸が幾重にも交差して、一枚の布となる。織物の仕事に込められた繊細な美しさを、ガラスの中に映し取った江戸切子《織々》。
グラス全体を覆うように配された直線的なカットは、まるで束ねられた糸のように見えます。色ガラスを細く残しながら精緻にカットされたガラス面が重なり合い、立体的な奥行きを生み出しています。
「織物って、単なる模様じゃなくて、構造そのものが美しいんですよね。その精緻さや温かみを、ガラスで表現できたらと思って」
どの角度から見ても異なる輝きを放つ設計。見た目の美しさだけでなく、手に取って楽しめる器としての実用性も大切にしているのが、青山作品の特徴です。
さらに、青山さんは今後の展開にも意欲的です。
「ロックグラスに加えて、ぐい呑みや小皿など、もっと形のバリエーションを増やしていきたいです。すでにデザインのストックもかなりあります」
次なる表現への構想は、すでに静かに進んでいるようです。
ひとしずくの風景をガラスに─《光雨(こうう)》という新作
この夏、新たに発表された《光雨(こうう)》は、青山さんの感性と技術が結晶したような作品です。
雲の切れ間から差す陽光と、きらめきながら降る大粒の雨。吉兆のしるしとされる「天気雨」の一瞬の美しさを映した《光雨》は、手にした方へ小さな幸福が訪れることを願って生まれました。
本作は、全国伝統的工芸品公募展にて「経済産業大臣賞」を受賞した作品でもあります。
自然の移ろいを切り取るようにして、凛とした美しさが宿る一品。
《光雨》では、上部をフロスト加工して雲を、下部に深いカットを施して雨粒と光のきらめきを表現。色ガラスを極限まで細く残し、透過光を計算した角度設計により、視線の角度や光のあたり方で異なる表情が浮かび上がります。すべての仕上げは手磨きによって行われており、だからこそ得られるクリアな輝きがあります。
「クリスタルガラスは細かく深いカットが可能で、その分カットの精度も求められます。また、一般的なガラスよりも透明度が高く、それらが合わさることで完成したときの輝きや陰影が全く違ってくるんです。」
デザインの着想について伺うと、「ふと目にした自然の風景から、イメージが立ち上がることが多いです」と青山さん。
「たとえば雨上がりの空、光の反射、水面の揺らぎ──そうした一瞬の情景に出会ったとき、“これをガラスで表現するならどうなるだろう?”と考えるんです」
まずはスケッチブックに描きとめることもあれば、ガラスを前にして、その場の感覚を頼りに直接デザインを彫り進めることも。自然との出会いがインスピレーションとなり、手の中でかたちを探っていくようにして、一つひとつの作品が生まれていきます。
職人として生きる

青山さんは、近年、伝統工芸士の認定も受けました。長年の技術研鑽と実績が評価されてのことです。
「道具の調整も自分で行いますし、現場で身体を使って覚えることばかりでした。先輩の手元を見て、真似て、数をこなして身につけていく。それしかない世界だと思っています」
また、女性職人としての現実的なハードルについても、率直に話してくれました。
「クリスタルはとにかく重たい。5キロや8キロの素材を扱うこともあって、体力は必要ですね。肩や首にくる負担は大きいです。」
ガラス職人の仕事には、長時間にわたって同じ姿勢を保ち、力の加減を繊細に調整しながら作業を続ける体力と集中力が求められます。
技術を身につけるには、ただ数をこなすだけでなく、その過程で身体への負担にも耐えていく必要があります。そうした厳しさに真正面から向き合いながら、淡々と、そして誠実に技を積み重ねてきた青山さん。
「そういうところも含めて、この仕事が好きなんです」と語るその言葉には、技術と感性だけでなく、静かな強さと覚悟がにじんでいました。

また、江戸切子といえば「男性的」な印象を持たれることが少なくありません。
重厚でシャープなカット、直線的な構図─そうした伝統的なイメージの中で、青山さんの作品は、透明感とやわらかさが共存する、やさしい空気感を纏っています。
「“こういう江戸切子もあるんですね”と言っていただけると、すごく嬉しいんです。もっと自由に、もっと多様な表現を提案していきたいですね」
伝統の枠にとらわれず、江戸切子に新たな息吹を吹き込む。その挑戦は、静かに、そして確かに進んでいます。
光を映す器で、日常にささやかな高揚を
「“使いたくなる江戸切子”を目指しています。飾るだけでなく、毎日の暮らしの中で楽しんでもらえるものにしたいんです」
その言葉通り、青山さんの作品は、ただの工芸品ではなく、手に取るたびに小さな感動が宿るような存在です。見る角度や光の差し方で表情が変わり、器がまるで呼吸しているかのように感じられる─そんな器。
インタビューの最後、青山さんがふとこんなことを話してくれました。
「日本工芸堂さんのことは以前から知っていました。SNSフォローさせていただいたのでありがとうございます。なんかすごく丁寧で、工芸を応援したいという気持ちがひしひしと感じられました」
そう言っていただけたことは、私にとってもこの仕事を続ける励みになりました。
工芸とは、技術の集合体であると同時に、その背景にある「想い」を伝える営みでもあります。これからも日本工芸堂では、青山さんの作品を、ただ販売するのではなく、その背景にある物語と言葉を丁寧に届けていきたいと考えています。

(写真:左、青山さん。右、日本工芸堂バイヤー松澤)
青山弥生|プロフィール
大学でインダストリアルデザインを学んだ後、「手でつくる仕事」に惹かれ伝統工芸の道へ。未経験から職人に弟子入りし、江戸切子の技術を一から習得。全国伝統的工芸品公募展で経済産業大臣賞を受賞し、2025年に「青山硝子工芸」を設立。
繊細で高度なカット技術と、手作業で仕上げる透明感ある磨きが高く評価されている。色ガラスを極限まで細く残すカット、光の透過を計算した角度設計など、設計段階からの美意識が随所に宿る。鋭さと柔らかさが同居するフォルムは、女性ならではの感性と職人の熟練が融合した証。見る角度によって表情が変わり、飾るだけでなく日常に溶け込む江戸切子を生み出している。
あとがき─繊細な光に出会った日
青山弥生さんの作品に初めて出会ったのは、ある展示で見かけた一連の切子でした。
これまで自社で扱ってきた、力強さを感じる切子とは趣が異なり、繊細さと静かな美しさが共存していて、自然と目を惹かれました。
しばらくして彼女が独立された直後、別の作り手の方との会話の中で偶然お名前が挙がり、「あの時の作品の方だ」とすぐに思い至りました。その後直接お話しする中で伝わってきたのは、作品づくりの背景にある丁寧な観察眼、積み重ねられた技術、そして“景色の一瞬をガラスに刻む”ような感性でした。
青山さんの切子には、装飾としての強さではなく、見る人や使う人に静かに語りかけてくるようなやさしさがあります。
色ガラスを極限まで細く残し、光の透過を計算したカットと手磨き仕上げによって、角度や光の加減で表情が変わる美しさが宿ります。作り手としての誠実な姿勢にも心を打たれ、ぜひこの切子を通して青山さんの静かな感性を届けたいと思いました。
| 【あわせて読みたい】 |
| > 「語る、工芸。」一覧はこちらから |