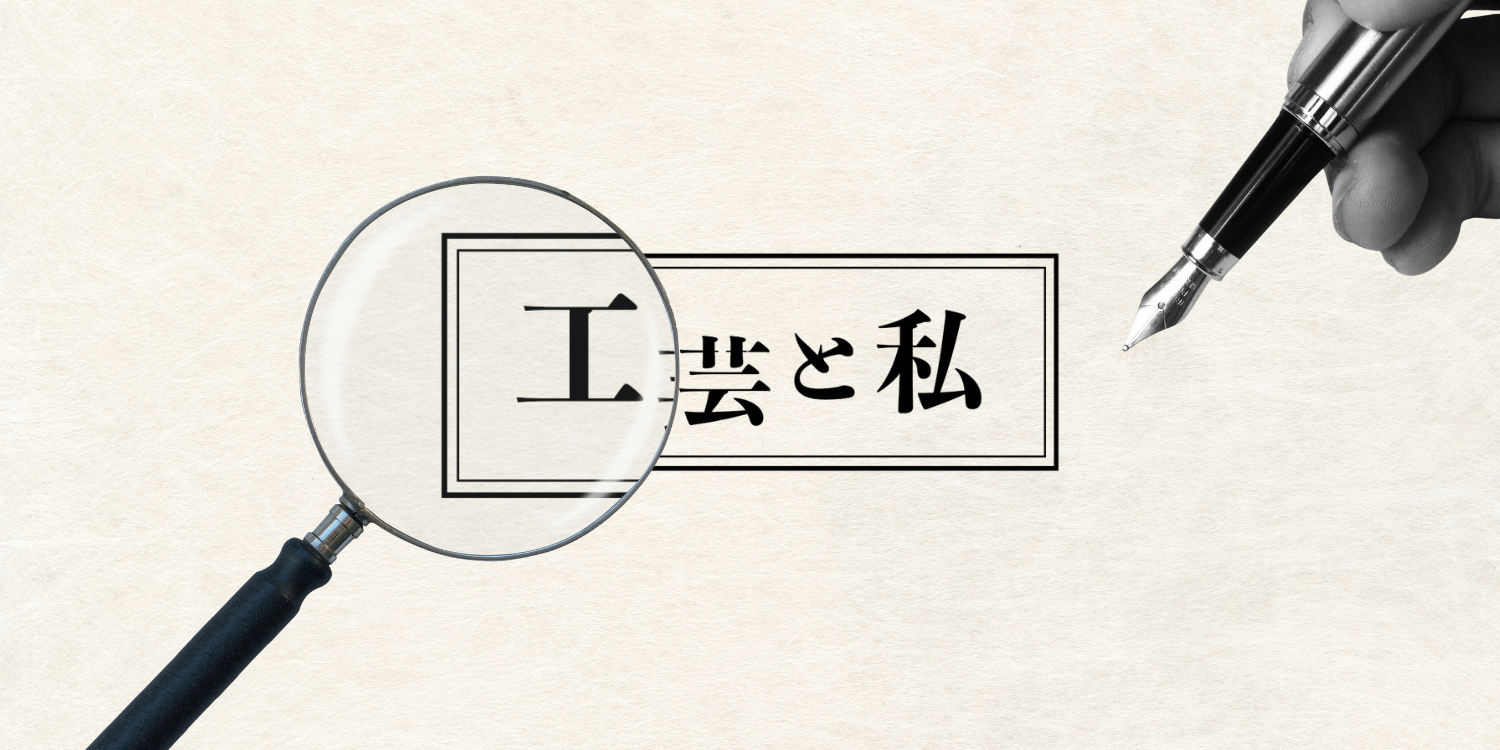
【工芸と私】語りかける手仕事/井坂 康志(ものつくり大学 教授)
本企画は、各分野で活躍する専門家が「工芸と私」をテーマに綴る寄稿シリーズです。異なる専門分野の視点から工芸の価値を捉え直し、現代における“ものづくり”の意義を探ります。今回は、日本工芸株式会社代表との長い縁をきっかけに、ものづくりを伝える立場からご寄稿いただきました。
現代はシンボルに覆い尽くされた時代である。
その中で工芸がシンボルに汚染されていないのは、一般にあまり注目されていないようだ。
元来ものづくりというものは、人間の精神を蒸留して、そこに形を与えたものである。自分の内面を正確に観察し、それを率直に映し出す。その観察力と造形力がしっかりしているほどに、成果物はいくらでも人の生活や心に入っていける。
これがシンボルばかりになると、すべての情報を外部にばかり探し求めて、肝心の人間の中身が見当たらなくなってしまう。極端に言えば、外にばかり目が行ってしまい、自分の心の中で何が進行しているのかわからなくなってしまう。
こういう傾向が強くなったのが現代だと考えると、工芸品の扱われ方が、ネット情報とはそのあり方において、まったく違っていることに気づくだろう。
工芸品の作り手は、詩人が言葉を選ぶように素材を選び、音楽家が音の配列に腐心するように日用の道具を造形していく。自分の内面生活が、そのまま生活の道具、たとえば茶碗とかグラスとか曲げわっぱに純化されたように感じている。
これがシンボルだとそうはいかない。いくらでもコピーできるし、頭脳は機敏に反応するけれど、感覚や肉体は休んでしまっている。
それに工芸品はコピーできない。だから、一つひとつそれほどうまくことが運ばず、苦心のうえに製作されているのは、素人の私でもわかることだ。それらの作品は、用いる人の生活や生理に直接働きかけるとともに、そのたびに知覚や感覚にも訴えかける。
私も日本工芸堂から品物をよく分けてもらう。
たとえば、私が毎日使うコーヒーカップは、私をよく知ってくれている。あたかも伴走してくれているかのように、働いてくれている。それは静止した物質のように見えて、生活に時間とともに深く分け入っていく。
それに、他になくて工芸品にあるものと言えば、物語である。もちろん私は有田焼や江戸切子の形式の美しさや色彩に心惹かれる。けれども、それ以上に心惹かれるのは、その背後にある職人の人生に流れたであろうそれぞれの時間、すなわち物語なのだ。私はその物語に身を任せる。
言葉は不要になる。口を利くことさえ野暮ったい。その形が、色彩が、手触りが、勝手に物語を語り出すからだ。私はそれに手を触れ、その語る声に耳を澄ませるさえすればいい。
あなたが手に触れる工芸品は、誰かが紡ぎ出した喜びの歌なのだ。あるいは、ある緊張した精神が生み出した暫定的な形なのだ。あなたは、その歌に耳を傾け、その形に手を触れる。どんな風に耳を傾け、どんな風に手を触れるかは、自分次第だ。
現代はシンボルのインフレの中にあって、頭脳的な情報処理においては達人だけれども、虚心坦懐に事物に触れることが難しくなっている。
日本工芸堂が取り扱うのは、現代におけるもう一つの物語なのだ。それがシンボルで汚染された現代人の心を浄化するもう一つの物語であることを私は固く信じている。

早稲田大学政治経済学部卒業。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、現在はものつくり大学教授(教養教育センター/ドラッカー経営学研究室)として教鞭を執る。ピーター・ドラッカーへの最後の外国人インタビューを行い、ドラッカー学会の共同代表も務める。経営思想と社会哲学の視点から、「つくること」の意味を問い続けている。
著書に『ピーター・ドラッカー―「マネジメントの父」の実像』(岩波新書、2024年12月)、『ドラッカー入門 新版―未来を見通す力を手にするために』(ダイヤモンド社、2014年8月・上田惇生共著)など多数。
あとがき:編集部より
情報に覆われる日常のなかで、静かに「触れること」「感じること」に立ち返らせてくれる一篇でした。
工芸を単なる“モノ”ではなく、“語る存在”として捉える視点が新たな気づきとなることを願っています。








