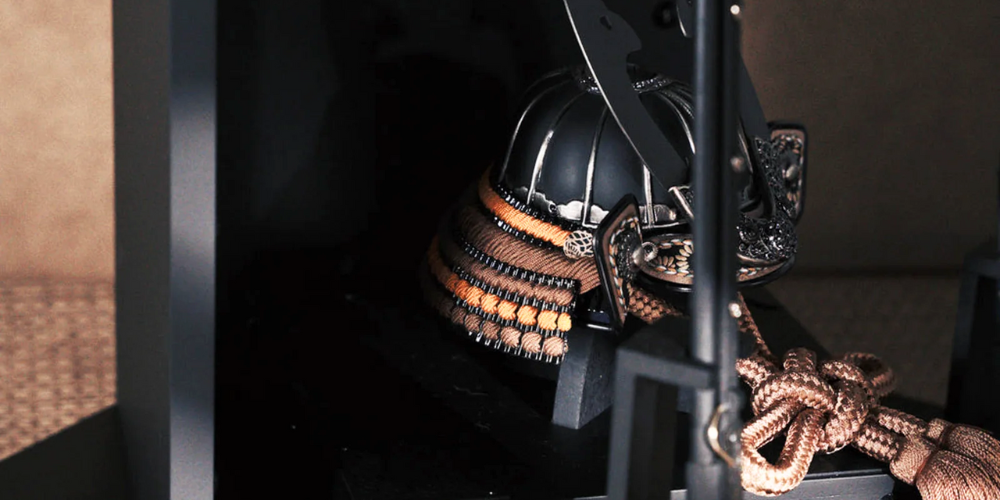酒器を選ぶときに知っておきたい、「ぐい呑み」と「おちょこ」の違い
日本酒を堪能する酒器といえば、ぐい呑みやおちょこが代表的です。しかし、ぐい呑みとおちょこでは、何が違うのでしょうか。この記事では、ぐい呑みとおちょこの定義とそれぞれの違いについて解説していきます。また、おすすめの伝統工芸品のぐい呑みとおちょこをご紹介。それぞれの違いを把握してお気入りの酒器選びの参考にしてみてください。
ぐい呑みとおちょこの違いとは?
日本酒を楽しむ酒器としてぐい呑みとおちょこがありますが、実はそれぞれ違った特徴があります。日本酒をさらに楽しむために、ぐい呑みとおちょこの定義やそれぞれの違いを説明します。
「ぐい呑み」とは
ぐい呑みとは、主に日本酒を飲むときに使用する酒器のことです。名前の由来は「ぐいっと呑む」や「ぐいっと掴んで呑む」などからきているとされていますが、明確にはわかっていません。
一般的には1〜2口では飲みきれないサイズのものが多いです。「ぐいっと呑む」などの由来からお酒をぐいぐい楽しめる大きさで作られているのかもしれません。素材は陶器やガラス、錫、木製など、さまざま素材で作られています。
「おちょこ」とは
おちょことは、ぐい呑み同様に日本酒を楽しむための酒器で、徳利とセットで使われることが多いです。
おちょこは漢字で「お猪口」と表記します。お猪口は、「ちょく(猪口)」が転じた言葉であるとされています。「ちょく(猪口)」とは、ちょっとしたもの表す「ちょく」や、飾り気のない安直なことを意味する「直(ちょく)」が語源となったと考えられています。
大きさは一口で飲み干せる程度のサイズが一般的です。
ぐい呑みとおちょこの違いは「大きさ」
ぐい呑みとおちょこの定義で説明したように、一番の違いは「大きさ」にあります。大きさといっても具体的に「何cm〜ぐい呑み」といった定義はありません。一口で飲み干せそうなのが「おちょこ」で、ぐいぐいと飲めそうなのが「ぐい呑み」といった程度の認識で大丈夫です。
また、猪口と言っても「そば猪口」のように、蕎麦つゆを入れる大きめの容器もあるので、一概にも大きさだけが違いだというわけではありません。
薩摩切子 冷酒おちょこ | 伝匠猪口 | 金紫 | 薩摩びーどろ工芸
ぐい呑みとおちょこを使い分けるには
基本的には好きなデザインや素材など、好みの器で楽しむことをおすすめしますが、お酒をより楽しむためにぐい呑みとおちょこの使い分け方も紹介します。
一口で飲み干せる大きさのおちょこには、冷たいままで飲みたい冷酒や香りを楽しみたい吟醸酒などがおすすめです。お酒は温度によって旨味や香りが変化するので、おちょこで少しずつ飲む方が、適温を保った状態でお酒が楽しめます。
反対に温度によって変化する味わいを楽しみたい方にはぐい呑みがおすすめです。純米酒は温度によって味や香りが変化するので、ぐい呑みで飲むことで一口ごとに変化が楽しめます。
関連記事:ぐい呑みとおちょこで味わいは変わる?日本酒は酒器で決まるのか
伝統工芸のおすすめのぐい呑み
ここまでは、ぐい呑みとおちょこの違いを紹介し、お酒の種類やシーンによって適した器あることを説明しました。伝統工芸品のぐい呑みはさまざまデザインや形がありますので、お酒の種類やシーンによって使い分けられます。おすすめの伝統工芸品のぐい呑みをいくつか紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
江戸切子のぐい呑み
江戸切子ならではの美しいカットが際立つぐい呑み。グラス表面には、竹垣を模した「矢来文様(やらいもんよう)」と、寒暖風雪に強い笹の葉を模した文様を、熟練職人の手で繊細に刻み込みました。
矢来文様には魔除けの意味が込められ、笹の葉の文様には健康長寿への願いが込められています。古くから大切にされてきた文様が、江戸切子ならではの透明感と輝きで表現され、特別な一杯を演出します。
純銀製のぐい呑み
日常の晩酌を特別にする、森銀器製作所の銀のぐい呑み。純銀のぐい呑みに日本酒を注ぐことで、日本酒が銀の輝きを反射し、いつもの日本酒がきらきらと輝く特別な一杯に感じられます。
天満切子のぐい呑み
宝石のように美しく、万華鏡のように輝く天満切子。「天満切子」は色被せガラスにU字型のカット(蒲鉾彫り)を施し、底の厚みを利用したカット模様が側面部分に映り込むことでいっそう輝きが増します。
天満切子 ぐい呑み | 杵型 十四縞 | 青 | 天満切子株式会社
伝統工芸のおすすめのおちょこ
ぐい呑みだけでなく、伝統工芸品のおちょこにもさまざまな素材やデザインのものがあります。形や大きさなどを比較して、自分だけのとっておきの酒器を選びましょう。
薩摩切子のおちょこ
鮮やかな色彩と一点物の輝きを放つ、薩摩切子のおちょこ。色ガラスと透明ガラスを高度な技術で密着させ、表面に繊細な文様を刻み込むことで生まれるグラデーションは、薩摩切子ならではの美しさです。

薩摩切子 冷酒おちょこ | 伝匠猪口 | 藍 | 薩摩びーどろ工芸
肥前吉田焼のおちょこ
日本酒をより美味しく彩ってくれる肥前吉田焼の美しい酒器セット。徳利と猪口には点描で花が描かれています。5つのブルーから色の組み合わせを選んでいただけるのもポイント。

肥前吉田焼 酒器 | 副久GOSU hana | 徳利・猪口箱入セット
鍋島焼のおちょこ
鍋島青磁の徳利、猪口、小鉢のセットです。
酒器はすべて1640年代、鍋島藩が技術習得のため職人につくらせていた中国・景徳鎮の「色絵山水竹鳥文輪花大皿」をモチーフに製作。
鍋島青磁 | 酒器セット | 徳利・猪口・小鉢 | 鍋島虎仙窯
錫のそばちょこ
四季の花を表現し、手作業で作られた錫のそば猪口「花ことば」シリーズ。そば猪口や向付にも使える仕様ですが、酒器として転用ができます。
酒器選びで日本酒をもっと美味しく
冬から春にかけてフレッシュな新酒が出回り、お正月など日本酒が飲みたくなる季節になります。おちょこで丁寧に味わうのもいいですし、ぐい呑みで豪快に飲むのも素敵です。
伝統工芸品の酒器は種類も豊富なので、いつもの晩酌を特別な時間にする自分用にも、大切な人へのプレゼントにも最適です。
まろやかな純米酒を楽しみたい方へ
▶ 陶器のぐい呑み・おちょこ 厳選
キレのある辛口酒・食中酒派へ
▶ 磁器のぐい呑み・おちょこ 厳選
香りを楽しむ吟醸酒派の方へ
▶ ガラスのぐい呑み・おちょこ 厳選20
燗酒をじっくり味わいたい方へ
▶ 漆のぐい呑み・おちょこ 厳選15
温度の変化を楽しみたい方へ
▶ 錫・金属のぐい呑み・おちょこ 厳選15
| 【あわせて読みたい】 |
| > 「伝統工芸の魅力」記事一覧 |