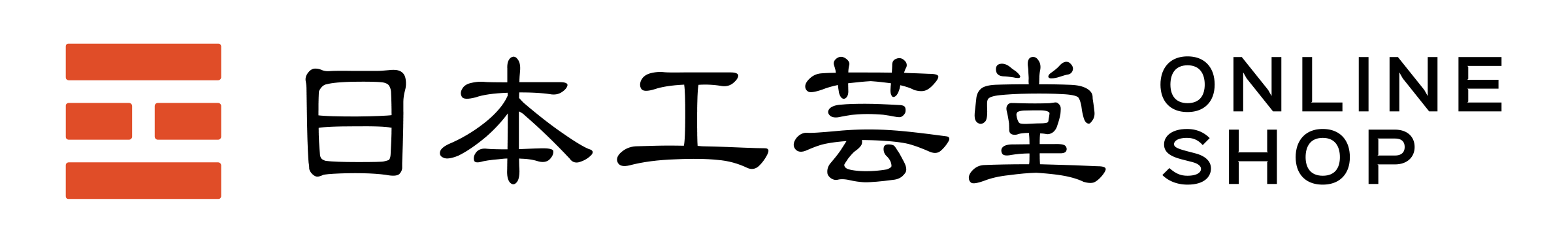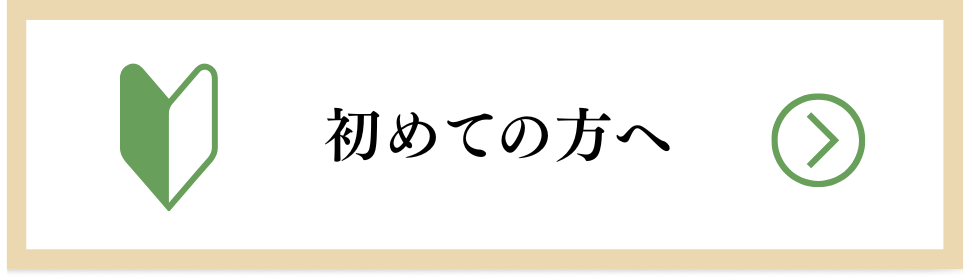記事: 【伝統工芸の旅】輪島塗と、売り続けるという関わり方

【伝統工芸の旅】輪島塗と、売り続けるという関わり方
震災以降、輪島という土地は、”復興途中の地”という言葉だけでは捉えきれない存在になりました。そこには、時間をかけて続いてきた仕事と、関係をつなごうとする人たちの営みがあります。
今回の輪島訪問は、そうした「いまの輪島」に立つ時間でした。
田谷漆器店さんのトレーラーハウスを拠点とした制作の現場に入り、沈金体験を通して、完成品になる前の工程に触れました。
その体験は、輪島塗を見る目や距離感を、これまでとは少し変えるものでした。
輪島塗を扱う小売の立場で、現地での体験と見聞を綴ります。
震災直前から続く、輪島塗との関係
輪島塗との取引を始めたのは、能登半島地震が起きる少し前のことでした。
工房を見学し、作り手の話を聞き、「これからしっかり紹介し、売っていこう」と考えた、その矢先に地震が起きました。
関係が生まれた直後だったからこそ、輪島は「遠くの被災地」ではなく、顔の見える人たちがいる産地として、強く意識に残る存在になりました。
その後、二度のチャリティ配信(2024年1月18日配信分詳細)を行い、現在も輪島塗の売上の1%を寄付する取り組みを続けています。また、田谷さんとは共催で工芸バーを実施し、輪島塗を知り、語る場をつくってきました。
どれも大きな支援とは言えません。
それでも、関係を途切れさせないために、私たちなりに選び続けてきた行動でした。
今回の輪島訪問は、そうした関係の延長線上にあります。
立場としてはイベント参加者としての訪問でしたが、これまでとは少し違う意味を持つ時間でもありました。というのも、今回初めて、トレーラーハウスを拠点とした「いまの輪島の現場」に立つことになったからです。

(写真:現在の田谷漆器の工房。震災後、トレーラーハウスを活用しながら、輪島塗の仕事が続けられています。かたちは変わっても、ものづくりの現場は止まっていません。)
沈金体験という「いまの輪島」に立つ時間
今回体験したのは、田谷漆器さんがアレンジされた沈金体験でした。
沈金(ちんきん)とは、漆器の表面に文様を彫り込み、その溝に金粉や金箔を埋め込んで装飾する伝統的な技法。ノミなどの工具で漆を掘り、彫り跡に漆を接着剤のように塗ってから金を押し込むことで、漆地と金の対照的な輝きが生まれます。
「沈んだ金」という名前が示すように、彫り込まれた溝に金が沈むように見えることが特徴です。輪島塗でも古くから用いられ、繊細で豊かな表現を可能にする装飾技法として重んじられています。
今回の体験では、あらかじめ決められた時間割に沿って進み、まずは沈金という技法について簡単な説明を受けた後、実際の作業に入ります。
まずは、漆を施した盤面を受け取るところから始まります。
そこに下絵を描き、その線に沿って道具を使い、盤面に切り込みを入れていきます。職人さんがすぐそばで手元を見ながら、「角度はもう少し立てたほうがいい」「ためらわず、線を入れていいですよ」と、都度声をかけてくれました。
 (写真:著者。沈金体験中の一コマ。線の濃淡は、道具の角度や力加減で大きく変わります。ためらわず線を入れることの難しさを、手の感触として知る時間でした。)
(写真:著者。沈金体験中の一コマ。線の濃淡は、道具の角度や力加減で大きく変わります。ためらわず線を入れることの難しさを、手の感触として知る時間でした。)
見ているだけのときには分かりませんでしたが、実際にやってみると、線の濃淡は道具の角度や力加減で大きく変わります。慎重になりすぎると、図案は盤面に浮かび上がりません。むしろ、ある程度の大胆さがなければ成立しない作業でした。
沈金は、繊細で静かな仕事という印象が先に立ちがちですが、その前段には、判断と決断の積み重ねがあります。すべての工程を体験したわけではありませんが、一瞬でも作業に加わることで、分業の一端を担ったような感覚が残りました。
完成品を見る目も、以前とは少し変わったように感じます。
職人との差は当然、圧倒ではありますが、その差の正体が体感として分かったことは、大きな収穫でした。

(写真:線の一本、余白の取り方、そのすべてが違います。輪島塗・漆芸沈金職人、前田さんの作品は、工程を知ったあとに見ると、なお美しく感じられました。)
>日本工芸堂、取扱の輪島塗の一覧はこちら
半年前と今回のあいだにあった時間
前回輪島を訪れた際は、輪島漆器商工業協同組合理事長・日南さんを訪ね、寄付をお渡ししました(詳細はこちら)。
その際にお話を伺ったのは、「自社の社屋は公費解体待ちなんです」という言葉でした。
建物は残っていて、使われなくなった空間として、そこに「在る」状態でした。
いつか解体されることは分かっていても、時間が止まったまま、静かに留まっているように見えたのを覚えています。
今回、その場所の前を通り過ぎたとき、風景は一変していました。
建物はすでになくなり、そこには平地だけが広がっていました。目印になるものが何もなく、意識していなければ、そのまま通り過ぎてしまいそうな場所でした。
これは復興が進んでいるということなのでしょうか。
それとも、ようやくゼロに戻っただけなのでしょうか。
正直なところ、どちらとも言い切れませんでした。
公費解体が進んでいること自体は事実として前進ですが、その「前進」が、関わってきた人にとってどのような時間として受け止められているのかは、外からは簡単に測れません。
前回と今回のあいだに流れた時間は、数字や工程表ではなく、目の前の風景として、静かに示されていました。

(写真:田谷漆器の元工房跡地に設置されたトレーラーハウス。今回の訪問で、初めてこの場所に立ちました。震災前とは違うかたちではありますが、輪島での営みが、いまも続いている現場です。)
小売店としての立ち位置を考える
こうした現場を見て、あらためて考えたのが、自社の立ち位置です。
私たちは職人でも、行政でも、支援団体でもありません。輪島塗を扱う小売店です。
今回、沈金体験を通じて、完成品としてではなく、制作の一端に触れる機会を得ました。
道具を持ち、線を引き、思うようにいかない感触を味わいながら、ほんの一瞬でもプロセスに加わったことで、これまでとは違う距離感が生まれました。
その体験には、「うまくできなかった」という実感と同時に、「関われた」という確かな手応えがありました。
完成品をただ手に取るのとは違い、工程の一部に触れることで、器や技法に対する見え方が変わる。その変化を、自分自身の中にはっきりと感じました。
この質感や感触、プロセスに加わったときの小さな喜びは、工芸品を「使う人」にも、同じような変化をもたらすのではないか。
そんな可能性を、あらためて考えるようになりました。
だからこそ、私たち小売店にできることは明確だと感じています。
輪島塗をきちんと伝えること。きちんと”売る”こと。
ただ「美しいもの」として並べるのではなく、背景やプロセスも含めて、「選ばれる商品」として紹介し続けることです。
支援らしい言葉を並べるよりも、売り場に出し続け、進化を見届けること。
体験を通じて感じた質感や時間を、言葉と場を通して丁寧に手渡していくこと。
それが、私たちにできる、輪島との関わり方なのだと思います。
 (写真:現在の工房内の様子。トレーラーハウスという限られた環境の中で、輪島塗の仕事が続けられています。特別な演出はなく、淡々と作業の時間が流れていました。)
(写真:現在の工房内の様子。トレーラーハウスという限られた環境の中で、輪島塗の仕事が続けられています。特別な演出はなく、淡々と作業の時間が流れていました。)
おわりに|輪島塗は、売り続けられることで残る
輪島塗がこれからどうなっていくのか、はっきりとした答えを持っているわけではありません。
ただ、輪島塗の歴史を振り返れば、これ以上の困難を乗り越えてきた時代もあったはずです。
分業の中で職人同士の互いの限界を競い合い、技を磨いてきた文化があります。その積み重ねは、一朝一夕で失われるものではありません。
私たちはこれからも、小売店として、輪島塗を売り、語り、紹介し続けていきます。それは、誰かの暮らしの中で使われる場所へきちんと送り出すためです。

写真:トレーラーハウス内に並ぶ、輪島塗のお椀。
美しさと実利性、そして背景をきちんと伝えること。それが、分業としての小売の役割なのだと感じています。
著者:松澤 斉之(日本工芸株式会社 代表)
編集:日本工芸堂 編集部
取材協力:田谷漆器店