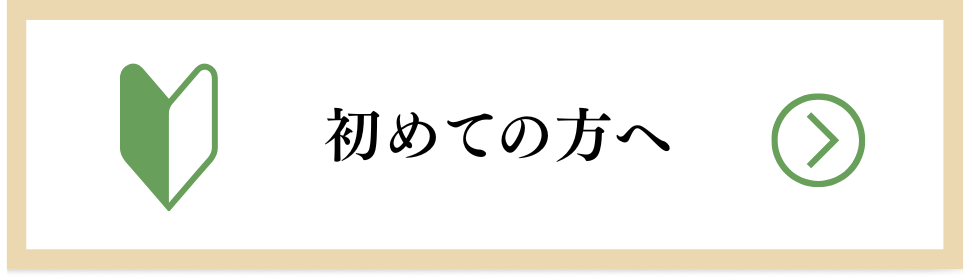【伝統工芸の旅】堺の現場を歩く|招へい商談会と工場視察レポート
堺市産業振興センター主催の「堺市伝統産業招へい商談会・工場視察」に、日本工芸株式会社(日本工芸堂運営)代表・松澤斉之が参加。商談会での対話、刃物・和晒・線香の工房視察を通じて、堺の伝統産業がいまどのような判断と更新のもとで成り立っているのか、その現場の姿を記録します。
はじめに|完成品ではなく、現場を見る
芸という言葉には、完成された美しさや、変わらない世界といったイメージが重ねられがちです。しかし、これまで現場に足を運ぶ中で私が向き合ってきた工芸は、常に判断と更新の連続でした。今回、堺の現場を歩いてあらためて強く感じたのは、人の判断によって更新され続けている“進行形の仕事”だということでした。
今回参加したのは、堺市産業振興センターが主催する「堺市伝統産業招へい商談会・工場視察、2日間」です。招へいという言葉は少し硬く聞こえますが、その実態は、産地側から「今の姿を、きちんと見てほしい」という意思表示でもありました。完成された成果を見せる場ではなく、商談や工房視察を通じて、現在進行形の取り組みや課題も含めて伝える。その前提に立つと、見る側にも姿勢が求められます。
完成した品を見るだけでは、その変化の気配にはなかなか気づけません。どこで迷い、どこで決断し、なぜその工程が選ばれているのか。その答えは、現場に立ち、作り手の言葉と手の動きを目の前で見て初めて、輪郭を持ち始めます。評価するために訪れるのではなく、理解するために立ち会う。だからこそ今回は、「もの」を見るのではなく、「現場」を見るために堺を訪れました。
 写真:堺伝承館では、包丁の製作工程における各段階の品を立体展示。 完成品だけでは見えない「途中の姿」が、工程への理解を深めてくれます。
写真:堺伝承館では、包丁の製作工程における各段階の品を立体展示。 完成品だけでは見えない「途中の姿」が、工程への理解を深めてくれます。
産地、堺の輪郭
初日に最初に訪れたのは、堺伝匠館でした。ここを訪れるのは二度目になりますが、いきなり個別の工房を見るのではなく、産地全体の輪郭をつかむ時間があらためて用意されていたことに、理解が一段深まる感覚がありました。堺には刃物、線香、染めをはじめ、複数の伝統産業が重なり合うように存在しています。
展示を通して見えてきたのは、堺が単一の産業で成り立つ場所ではなく、分業や連携の中で文化を育んできた産地だということでした。この全体像を最初に提示する構成からは、個々の技術だけでなく、地域として伝統産業をきちんと伝えていこうとする明確な意志が感じられます。
産地の全体像を共有したうえで商談会や工房視察に向かうことで、目の前の仕事が、堺という地域の中でどのような役割を担っているのかを考えながら見ることができます。この視点が、この後に続く対話や現場を見る時間の基準を、自然と整えてくれました。

写真:堺伝匠館 – SAKAI TRADITIONAL CRAFTS MUSEUM
商談会という現場
初日午後は場所を移し、商談会が行われました。ここで交わされていたのは、取引条件の確認にとどまらず、それぞれの現場が今どのような状況にあり、どこまで責任を持ってものづくりができるのかを共有する対話でした。
各事業者の説明は簡潔で、過剰な売り込みはありません。その代わりに語られていたのは、生産量の限界や人手の状況、どの工程に最も時間がかかっているのかといった、日々の現場に直結する話です。話を聞くうちに、商品がどのような環境の中で作られているのかが、少しずつ具体的になっていきます。
包丁をはじめとする刃物の分野は、海外からの需要が非常に強く、すでに作りきれない状況にあることは以前から知っていました。それでも、ただ量を増やすのではなく、自社の強みが生きる品揃えに絞る、新たなブランドとして切り分ける、供給体制を無理のない形に整えるなどの選択意思を伺うことができました。そこには、注文があるから作るのではなく、作り続けられる形をどう保つかという視点があります。
完成品だけを見ていては分かりにくいこうした背景を知ることで、ひとつの道具がどれほど多くの調整や判断の積み重ねの上に成り立っているのかが、自然と想像できるようになります。この商談会は、商品を選ぶ側にとっても、その一歩手前の現場に触れるための時間だったように感じました。

 >自治体での活動実績一覧はこちら
>自治体での活動実績一覧はこちら
工房を視察する意味
工房を見るということは、ひとつの会社や技術を知ることにとどまりません。今回は二日目の視察として三社を訪ね、それぞれの個社の事情や判断について話をうかがいましたが、それ以上に印象に残ったのは、これらの産業がどのような歴史と結びつき、地域の中で形づくられてきたのかという点でした。
なぜこの場所でこの仕事が続いてきたのか。時代の変化の中で、何を残し、何を変えてきたのか。工房という現場でそうした話を直接聞けることは、完成品だけを見ていては得られない理解につながります。
産業を点ではなく、時間と地域の連なりとして捉え直す、その意味でも、今回の視察は非常に有意義な時間でした。

写真:薫明堂では、線香ができる製造過程を一つひとつ見せていただきました。原料を扱う工程では、想像以上に香りが強く、天然素材そのものの存在感を肌で感じます。

写真:山脇刃物製作所。ここは二度目の訪問となりました。変わらず工房には研ぎの音が響き、刃と向き合う職人の手の動きから、現場の緊張感が伝わってきます。
山脇刃物製作所、進行形の堺打刃物
回の工場視察の中で、改めて印象に残ったのが、山脇刃物製作所への視察時間でした。 ここを訪れるのは今回が二度目で、すでに取引もあり、製品は国内外で広くご購入いただいています。
堺打刃物は、「鍛造」「研ぎ」「柄付け」を分業で行う体制が基本です。山脇刃物製作所では、そのうち「研ぎ」と「柄付け」を担い、一本ずつ仕上げた包丁を出荷しています。
説明を受ける中で印象に残ったのは、職人が刃を見るときの「目の使い方」でした。反りや厚み、研ぎの進み具合を確かめながら、次に進むか、ここで止めるかをその場で判断していく。その決断は、数値や手順だけではなく、目と感覚に支えられています。
「研ぎ」や「柄付け」といった工程では、刃の状態をどう捉えているかが、そのまま判断の拠り所になっているようでした。
そうした話を聞き、実際の作業を目にする中で、堺打刃物が過去の技術として保存されているのではなく、判断を重ねながら更新され続けている仕事である理由が、自然と理解できました。
すでに評価や実績があり、安定して使われている包丁であっても、現場では一本ごとに判断が繰り返されています。 山脇刃物製作所は、堺打刃物の分業体制の中で、最終工程を担いながら、その「進行形」を静かに支え続けている現場でした。
>山脇刃物製作所、お取り扱い品一覧ははこちら

写真:光にかざして刃の歪みや偏りを目で確認し、必要に応じて叩きながら形を整えていく過程。
和晒の現場、時間をかけるという選択
今回訪れたのは、石津川のそばに製作所を構える、堺の伝統産業「和晒」を手がける角野晒染株式会社でした。
現在、堺で和晒を続ける工房は数軒を残すのみですが、かつては綿布を川で流し、近くの山まで運んで天日干しをする光景が日常だったといいます。土地と水、そして時間が、そのまま仕事の条件になっていた場所です。
和晒(わざらし)とは、織り上がった綿布を大きな釜で約30時間煮立て、油分や糊などの不純物を数日かけて取り除いていく、日本独自の晒しの方法です。
 (写真:生成りの綿布を釜に入れ、約30時間煮込む和晒工程の準備段階。 ここから、繊維に負担をかけずに布の状態を整えていきます。)
(写真:生成りの綿布を釜に入れ、約30時間煮込む和晒工程の準備段階。 ここから、繊維に負担をかけずに布の状態を整えていきます。)
薬剤で短時間に白さを引き出す洋晒とは異なり、繊維に無理をかけず布の状態を整えていくため、仕上がりはふっくらと柔らかく、吸水性や通気性にも優れます。使い続けるほどに風合いの差が出てくる点も特徴です。
和晒の現場で印象に残ったのは、「どれくらい時間がかかるか」ではなく、「なぜその時間をかけるのか」という考え方でした。用途や求められる質を起点に、時間をかけることが最も適している場合が選ばれている。その判断をもとに、工程が組み立てられています。
角野晒染では、染めの技術を一つに固定していません。量や用途、求められる風合いに応じて、技法や工程を選び分けています。そこには常に、「いま、この布には何が合っているか」という判断が先にあります。変化するニーズに向き合いながら、その都度、現場で答えをつくっている印象でした。
和晒は、過去の製法として残されているものではありません。布の性格を見極め、工程を選び直しながら更新され続けている、現在進行形の仕事なのだと感じられました。

三つの現場から見えたこと
刃物、和晒、線香。 三つの現場を巡りながら共通して感じたのは、堺の伝統産業が「技術」そのもの以上に、「判断」によって支えられているということでした。
刃物では、研ぎの一瞬の判断が、そのまま形として現れます。 和晒では、判断はすぐに結論を出すものではなく、工程を重ねる中で、少しずつ結果として立ち上がってきます。 線香づくりでは、目に見えない香りの質を探りながら、わずかな違いを見極め続けていく。
そして印象的だったのは、どの現場でも「昔からこうしてきた」という説明が前に出てこなかったことです。 代わりに語られていたのは、「今の状況に、何が合っているか」という問いでした。 堺のものづくりは、完成された型を守るというより、選び続ける行為そのものによって更新されている。そんな現在地が見えてきます。
こうした現場を知ると、ものを選ぶ視点も自然と変わってきます。 価格や条件だけでなく、安定して届けられるか、品質がきちんと再現されるか、その背景にどんな考え方があるのか。 「何を選ぶか」だけでなく、「なぜそれを選ぶのか」という基準が、より大切になっていきます。
工芸品は、完成された答えとして存在しているわけではありません。 判断と時間を重ねながら、今も更新され続けている途中の存在ではないでしょうか。 そのプロセスを知ったうえで手に取ることで、使う側もまた、その続きを担っているような感覚が生まれます。
工芸が進行形であり続ける限り、選ぶ側の姿勢もまた、固定されるものではありません。完成された答えではなく、選び続けている途中に立ち会うこと。 その距離感こそが、工芸と長く付き合っていくためのヒントになるように感じられました。

著者:松澤 斉之(日本工芸株式会社 代表)
編集:日本工芸堂 編集部
取材協力:
堺市産業振興センター(堺伝承館)
視察先各社(山脇刃物製作所/和晒工房/線香製造各社)