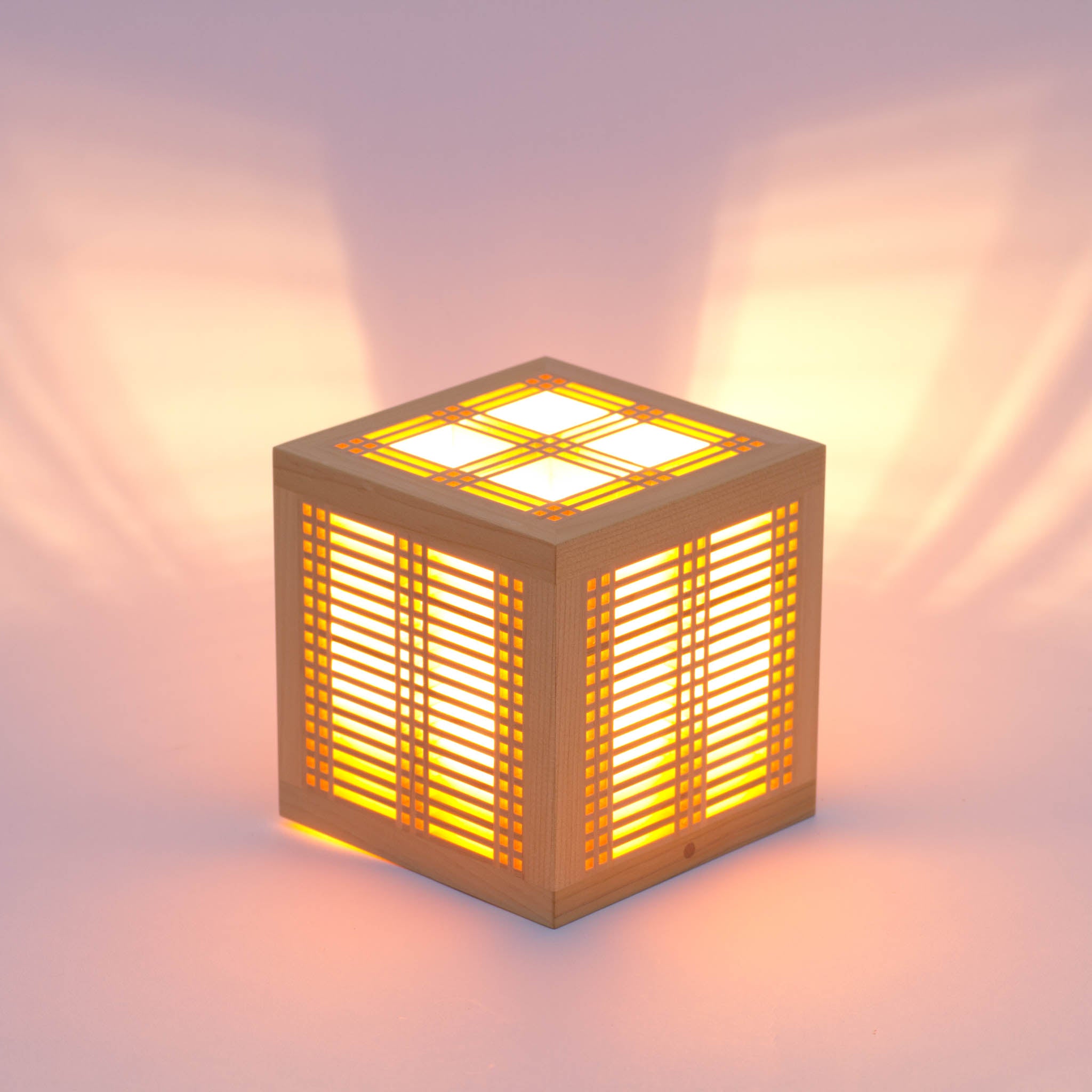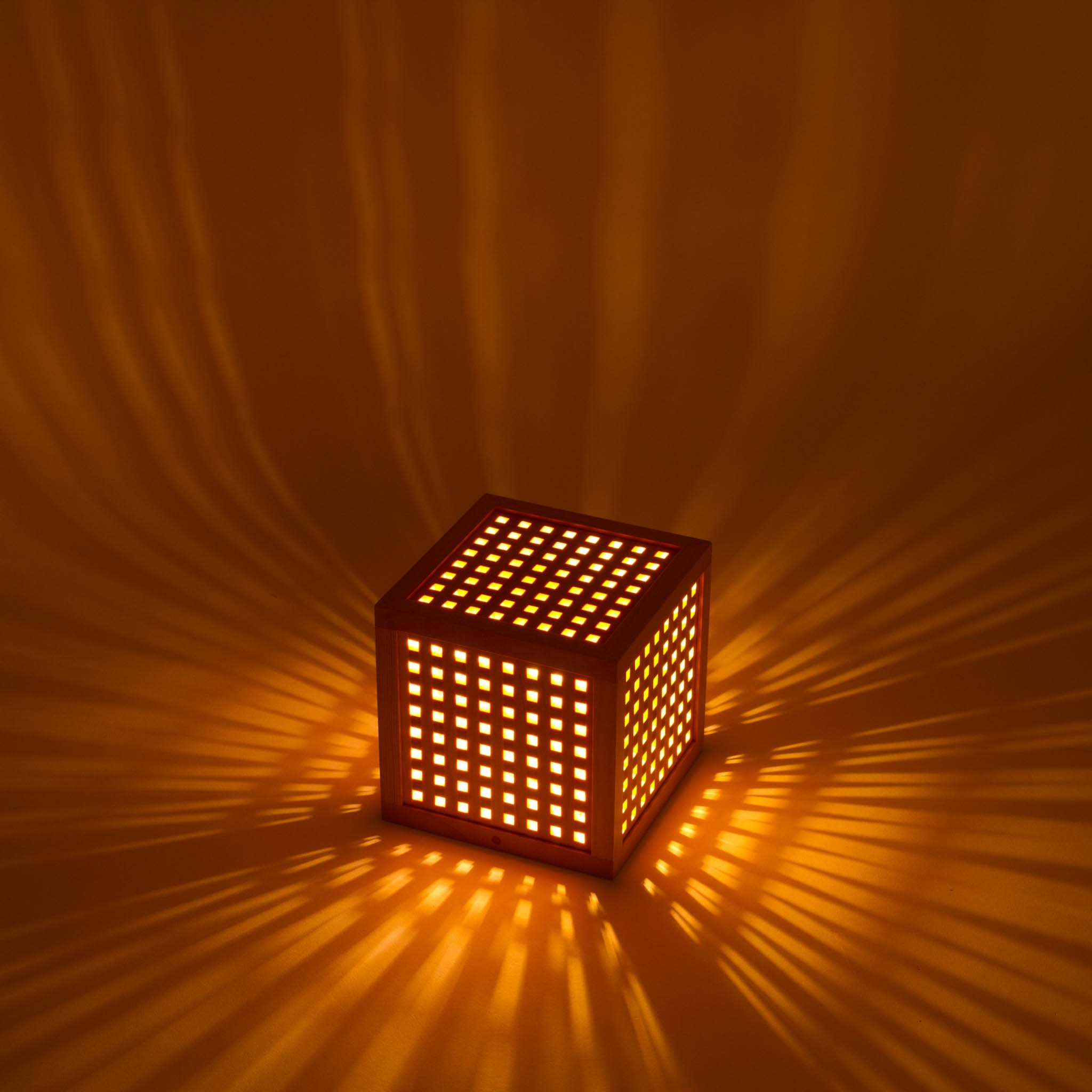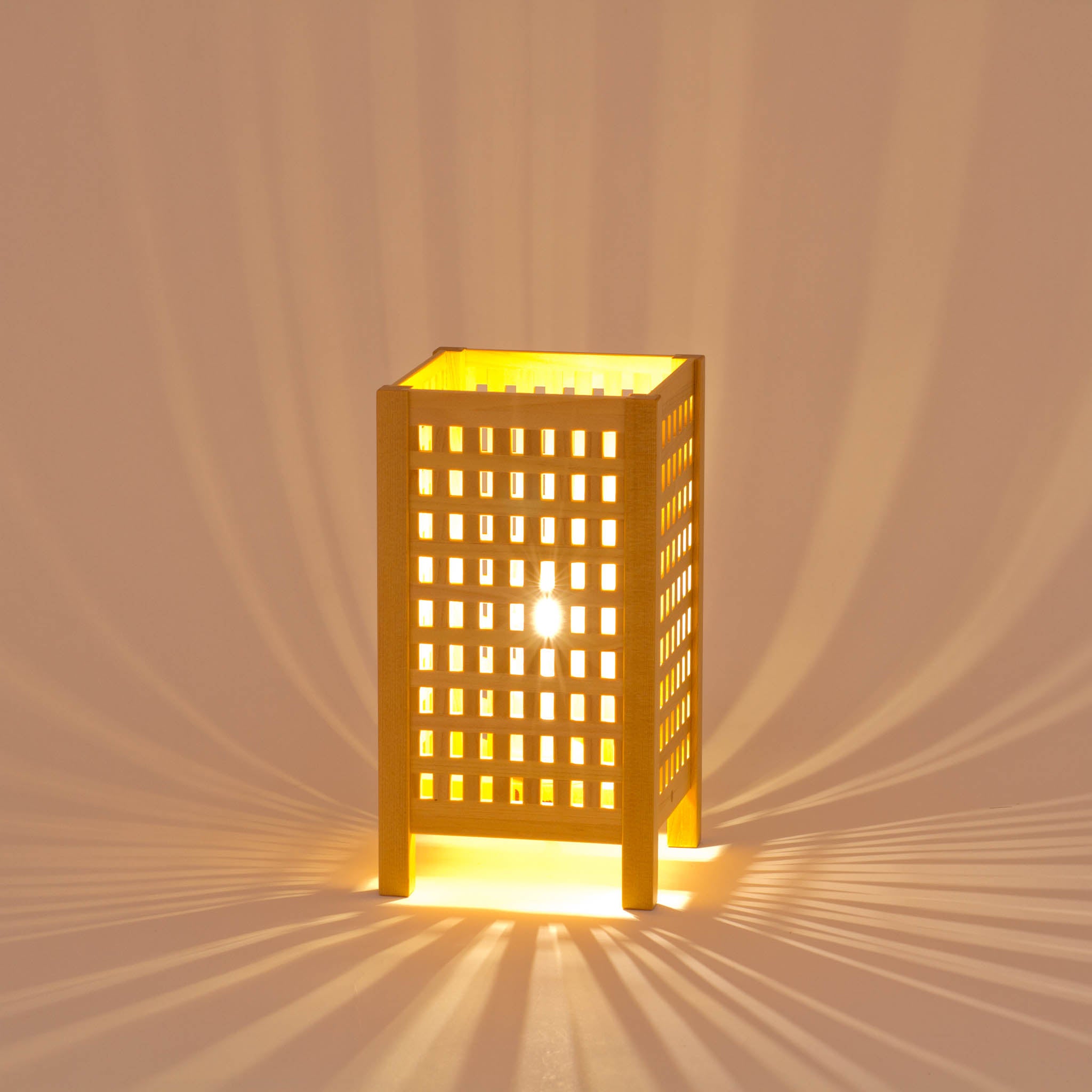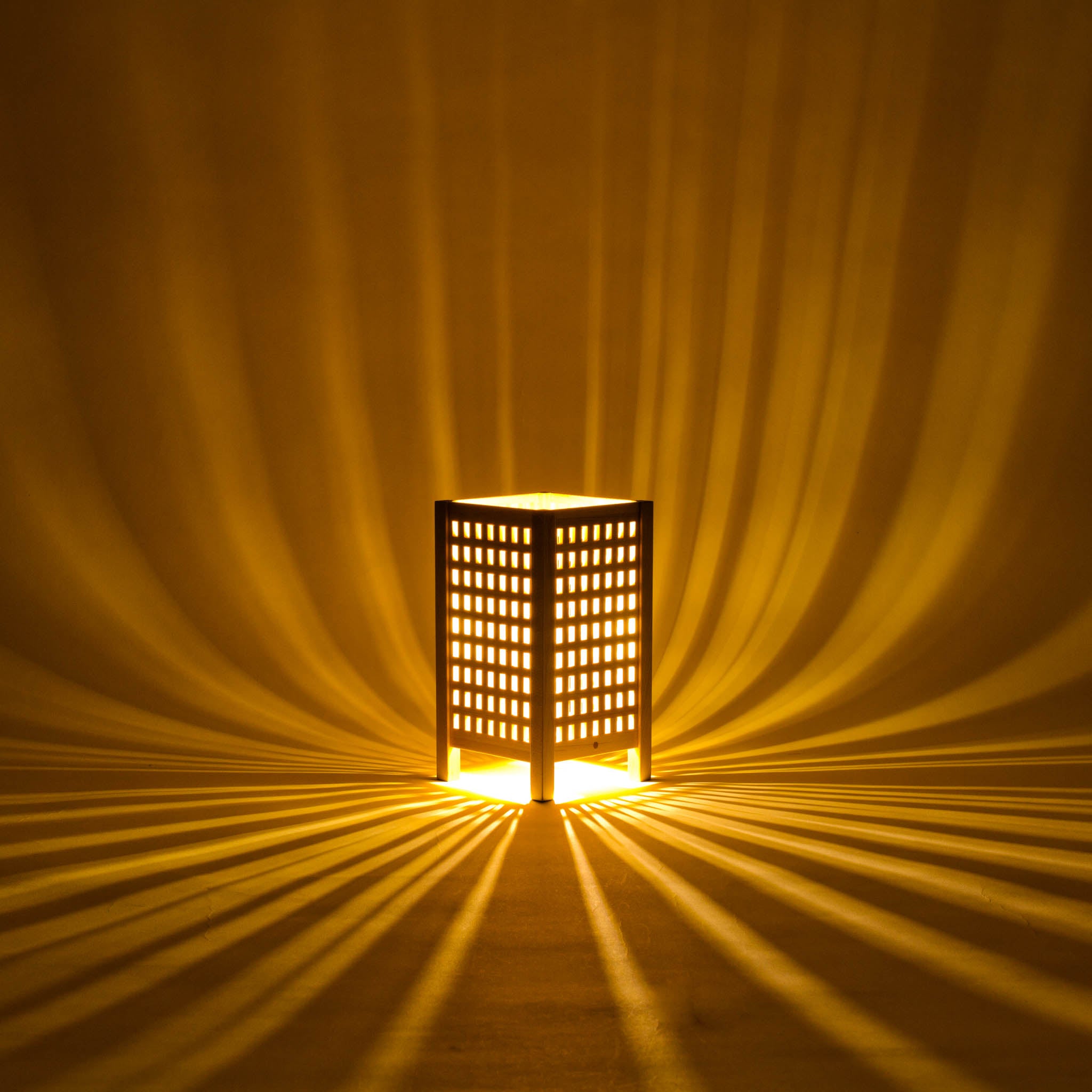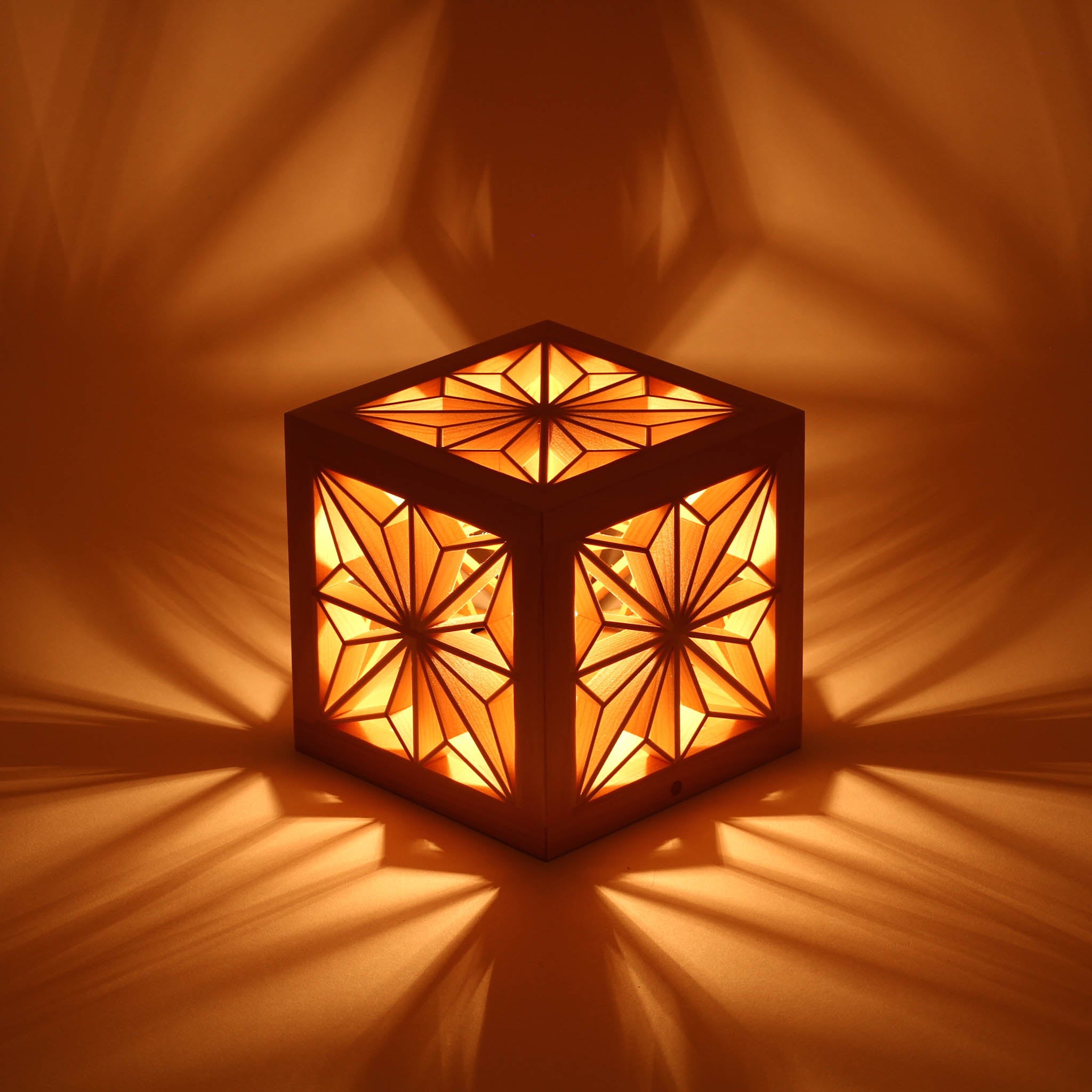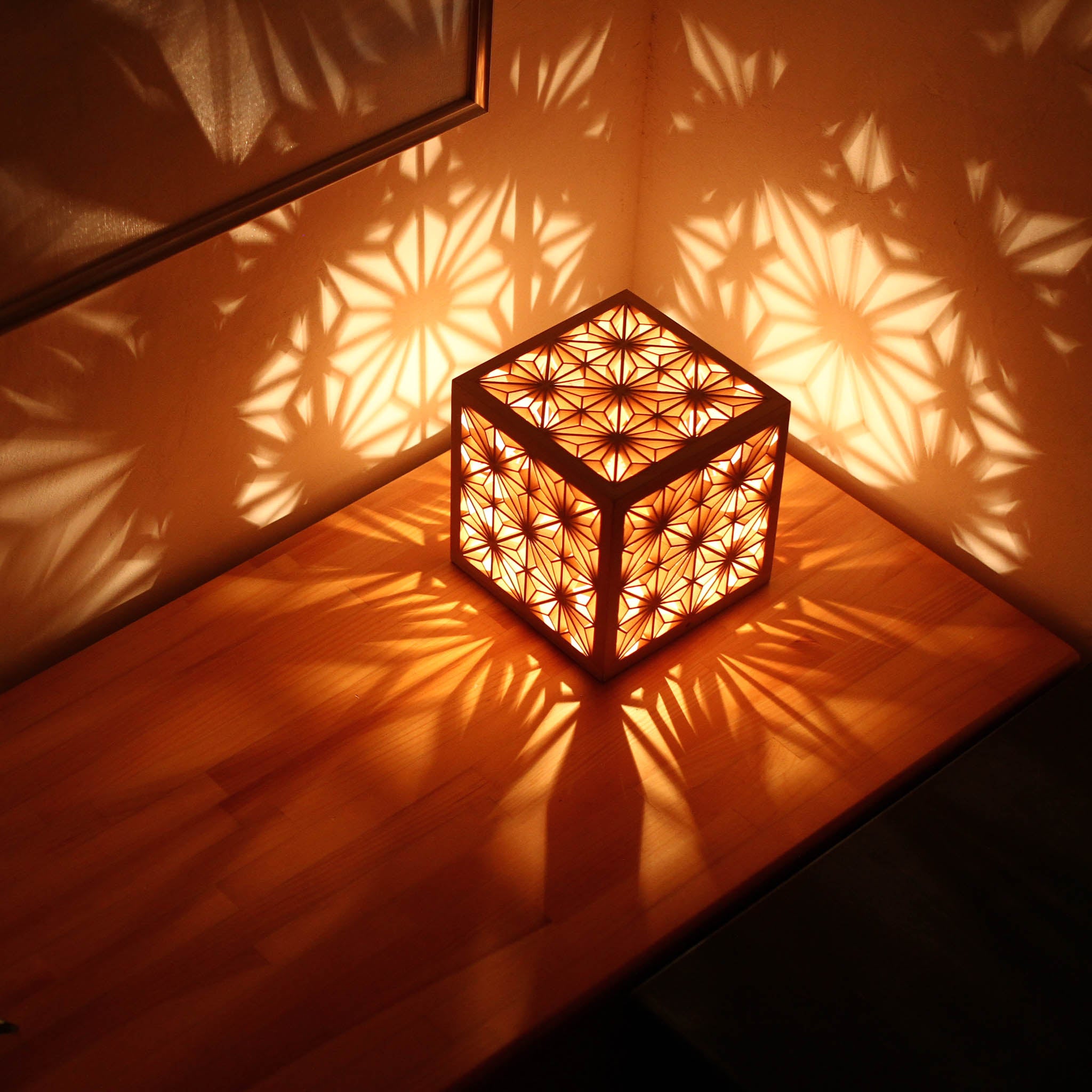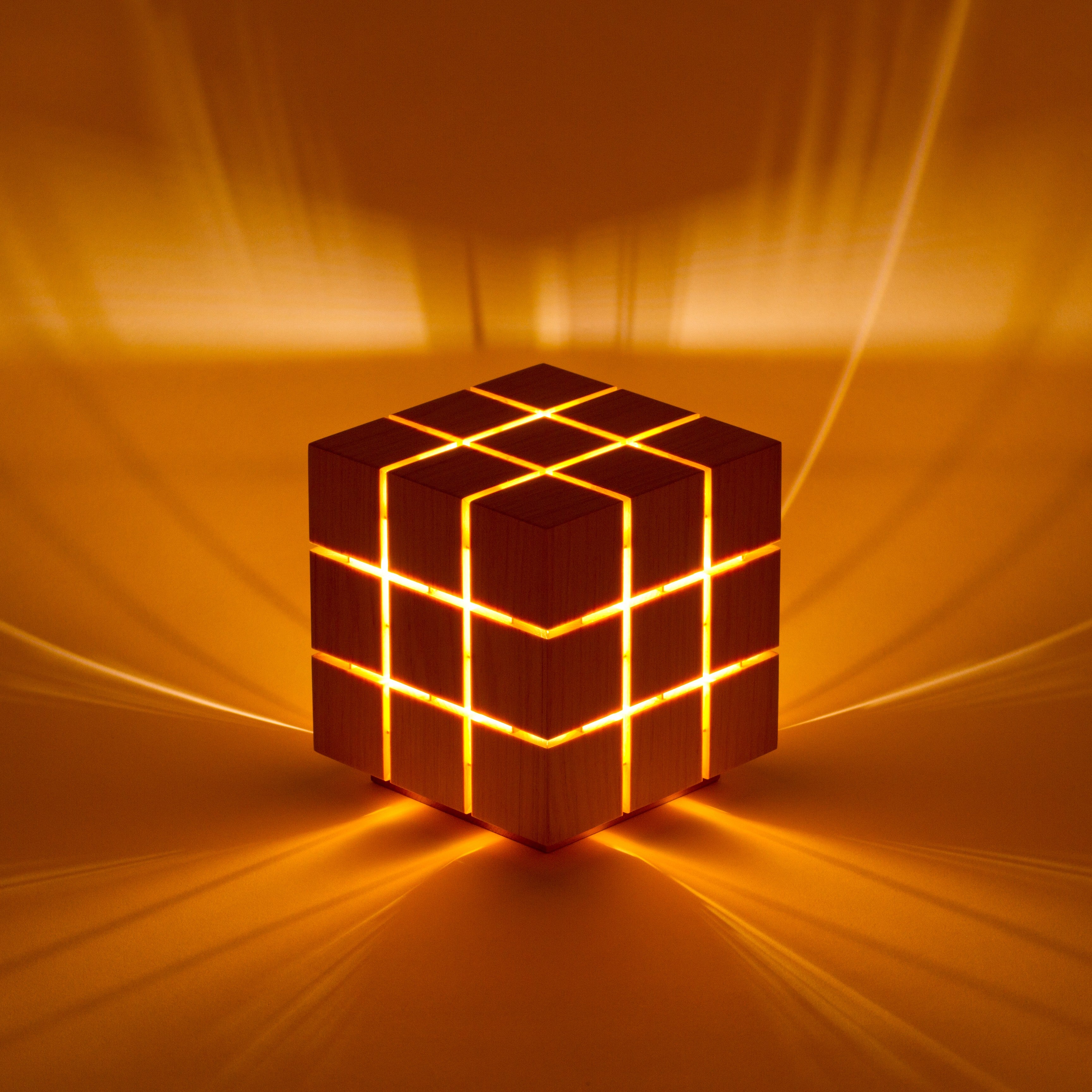フィルター
組子細工 テーブルランプ | ひかりの小箱1 | 木のあかり
¥13,200
組子細工 テーブルランプ | ひかりの小箱2 | 木のあかり
¥13,200
組子細工 テーブルランプ | かがやき | 木のあかり
¥13,200
組子細工 テーブルランプ | 雫 S | 木のあかり
¥13,200
組子細工 テーブルランプ | 輝羅 S | 木のあかり
¥27,500
組子細工 テーブルランプ | 麻の葉キューブ S | 木のあかり
¥33,000
組子細工 テーブルランプ | 麻の葉キューブ M | 木のあかり
¥110,000
組子細工 テーブルランプ | 麻の葉キューブ D | 木のあかり
¥66,000
組子細工 フロアランプ | 麻の葉格子 | 木のあかり
¥154,000
組子細工 テーブルランプ | イルタミナ | 木のあかり
¥11,000
組子細工 テーブルランプ | 集 S | 木のあかり
¥29,700