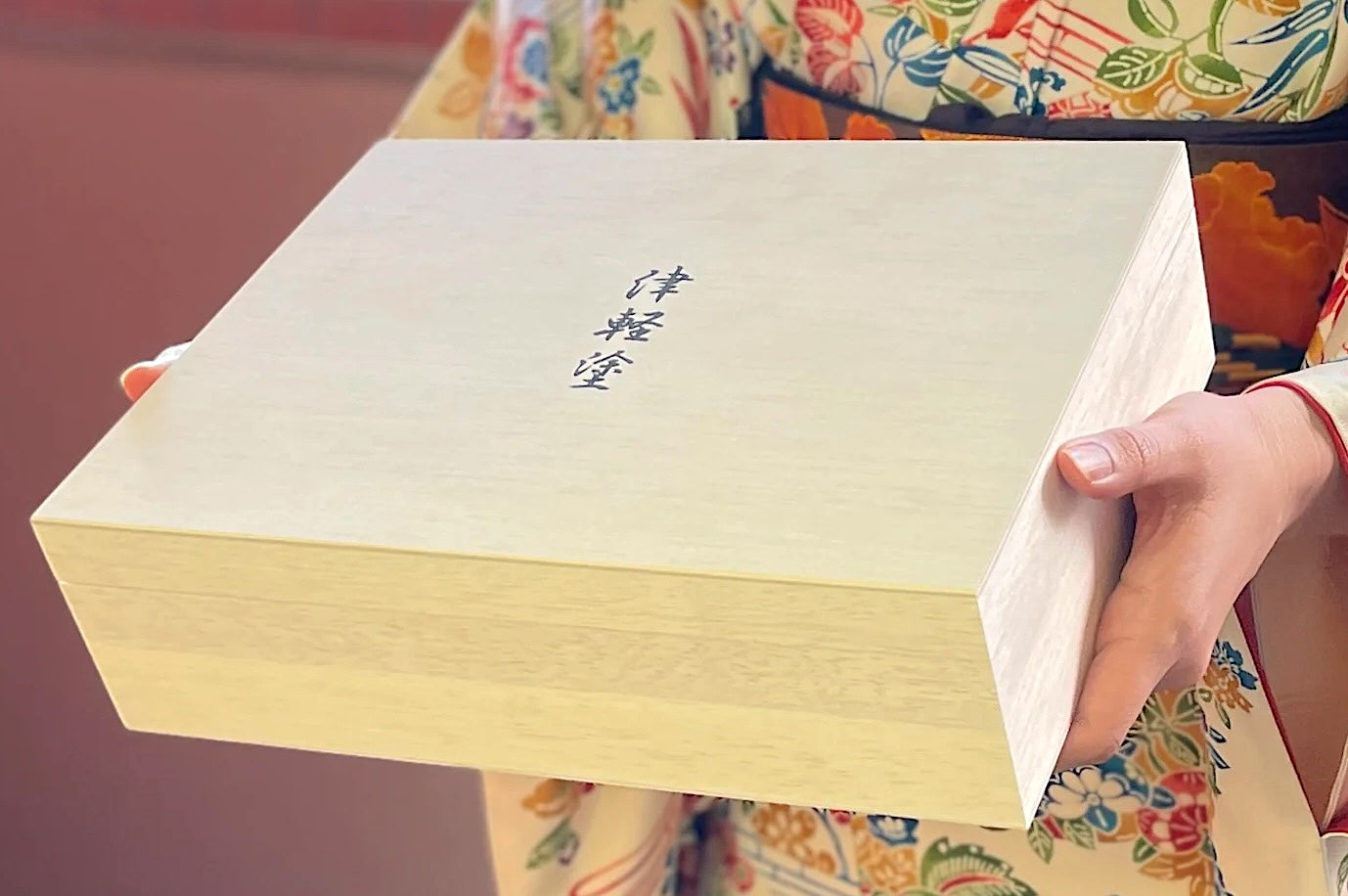【伝統工芸の旅】益子焼の里を訪ねて(栃木)
日本各地には、その土地ならではの伝統工芸を受け継ぐ職人や工房があり、日本の文化を支えています。日本工芸堂の代表・バイヤーの松澤が作り手をたずねる「伝統工芸の旅」。今回は、東京からのアクセスも良く、若手作家が多く活躍する栃木県益子町を訪れました。益子焼の魅力と、それを支える人々の想いに触れる旅をご紹介します。

益子焼との出会い
益子焼は、江戸時代末期に始まり、日用品としての陶器を中心に発展してきました。その特徴は、厚みのある素朴な風合いと、温もりを感じさせる手触りにあります。益子町は、首都圏からのアクセスが良く、若手作家が多く集まる地域としても知られています。
私が初めて益子を訪れたのは、2022年3月。栃木県産業技術センター窯業技術支援センター主催の「とちぎの器」魅力向上研究会に、海外向けバイヤーとして招聘いただいたのがきっかけ。この研究会は、益子焼、小砂焼、みかも焼などの伝統的な陶磁器産業の需要減少に対応し、海外市場への展開を目指して商品開発や販路開拓、PR活動を行うプロジェクトです。*報告書はこちら「とちぎの器」魅力向上研究会(海外展開)活動報告書
私はこのプロジェクトにアドバイザー参加し、指定された製陶事業者が海外展開やオンライン販売を行う際の留意点について意見を求められました。その後も何度か益子を訪れ、益子焼の奥深さに惹かれ続けています。

益子焼の魅力と特徴
益子焼は茨城県や他地域から取り寄せた陶土も使われつつ、地元産の陶土も用いられ、厚手で重厚感のある器が特徴です。ざらりとした質感やぽってりとした丸みのあるフォルムは、どこか懐かしく、自然の温もりを感じさせます。
多彩な釉薬も益子焼の魅力のひとつ。飴釉(あめゆう)、黒釉(こくゆう)、糠白釉(ぬかじろゆう)など、それぞれが深みのある表情を生み出し、ひとつとして同じものがない個性豊かな器に仕上がります。
実用性の高さも見逃せません。丈夫で壊れにくく、和洋どちらの料理にも馴染むデザインは、毎日の食卓を美しく彩ります。最近では、若手作家やデザイナーとのコラボレーションも盛んで、シンプルでモダンな作品も数多く誕生しています。伝統と革新が共存する益子焼は、使う人の感性に寄り添い、日常に彩りをもたらしてくれます。
歴史に触れる:益子焼のはじまり
益子焼の歴史は、1853年(江戸時代末期)、笠間焼で修行を積んだ大塚啓三郎が益子に窯を築いたことに始まります。生活用品としての陶器づくりが発展する中、大正時代には柳宗悦が提唱した「民芸運動」の流れを受け、陶芸家・濱田庄司が益子に移住。彼は「用の美」を大切にした作品を生み出し、益子焼の芸術性と実用性を全国に広めました。
この民芸運動により、益子焼は「日々の暮らしの中にある美」として再評価され、地域の文化として深く根付いていくことになります。現在もその精神は脈々と受け継がれ、多くの作り手が独自の表現を追求し続けています。
関連記事:日本の「用の美」を伝える伝統工芸品とその継承にむけて

益子で楽しむ、伝統とモダンの交差点
益子町には、伝統と革新が共存するスポットが数多く存在し、町歩きの中でその魅力を肌で感じることができます。特に「城内坂通り」は益子の中心地として知られ、益子駅から徒歩約15分、約500メートルにわたって個性豊かな店が軒を連ねています。
益子焼窯元共販センター
日用食器から有名作家の作品まで幅広いラインナップを誇る大型施設。正面には日本一大きな狸の置物があり、写真スポットとしても人気です。隣接する食事処やギャラリーもあり、家族連れでも楽しめます。

陶庫(とうこ)
城内坂通り交差点付近にある和モダンな雰囲気が魅力のショップ。日常使いの食器からアート作品のようなオブジェまで、さまざまな作家による作品が並びます。見るだけでも楽しく、手仕事の温もりを感じられる空間です。
お食事処 杣
創業42年の本格和食店です。地元の有機野菜や肉を使用。益子焼の器で料理を提供。地産地消にこだわり、季節ごとの素材を最大限に活かした定食や一品料理を楽しめました。研究会に同席されていた地元酒蔵社長さんにお連れいただきました。

藍染の伝統に触れる:日下田藍染工房
益子は陶器だけでなく、藍染の伝統も受け継がれています。城内坂の入り口に佇む日下田藍染工房は、寛政年間(1789〜1801年)創業と伝わる歴史ある藍染工房。茅葺屋根の古民家で営まれており、静寂と風格が漂うその佇まいは、訪れる人を江戸時代へと誘います。
母屋には70基を超える藍甕が整然と並び、藍染の作業場では職人が一つひとつ丁寧に染め上げる様子を間近に見ることができます。藍色が何度も染め重ねられることで深まっていく様子は、自然の力と職人の技が融合した美しさそのものです。
工房内では藍染の衣料品や小物も販売されており、ここは単なる観光地ではなく、藍染の真髄と職人の情熱を肌で感じられる、特別な場所となっています。
おわりに
益子町は、焼き物と藍染という二つの伝統が息づく、文化の豊かな土地です。器に触れ、作り手と話し、町を歩くことで、その奥深い魅力を存分に味わうことができます。益子焼の素朴な美しさと、藍染の静かな情熱。どちらも日々の暮らしに寄り添いながら、私たちに日本の美意識の豊かさを教えてくれる存在です。
私自身、声をかけていただきコメントをする立場で何度か足を運びましたが、回を重ねるごとにそのゆったりとした空気感に惹かれ、すっかりファンになりました。陶器市の時期は多くの人で賑わうそうですが、静かな季節にのんびりと巡る益子の町もまた格別です。
東京からの小旅行にも最適な益子町。ぜひ、ご自身のペースで訪れてみてはいかがでしょうか。