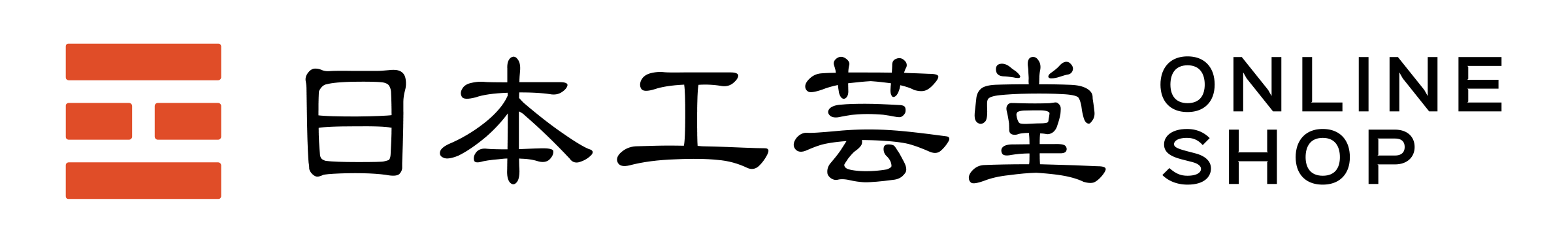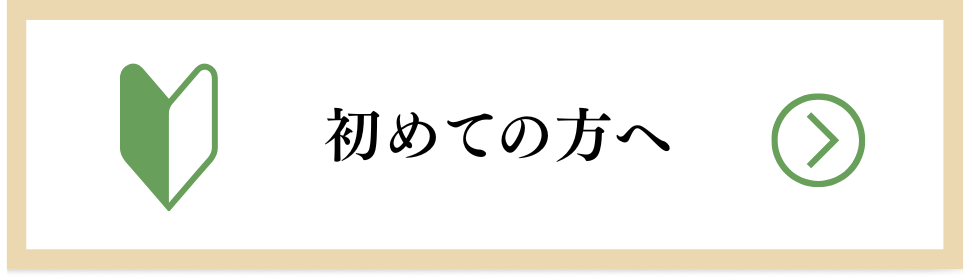薩摩びーどろ工芸
幻の薩摩切子を蘇らせた、一流職人の手仕事
薩摩切子が生まれたのは弘化3(1846)年。薩摩藩主島津家が産業振興のために製造を推奨したことが始まりです。しかし、ガラス製造を推進していた島津斉彬の急逝と薩英戦争による工場への攻撃で、切子製造は途絶えてしまいました。
その後、約120年を経た昭和60(1985)年、斉彬ゆかりの地にガラス職人が集結しました。試行錯誤の上、かつて世界を魅了した薩摩切子の復元に成功した。世界でも珍しい金赤や黄などの色ガラスを開発していた薩摩の硝子が、現代に蘇りました。
薩摩びーどろ工芸が目指すのは、そんな薩摩切子を忠実に受け継ぐことです。文献を徹底的に研究し、当時の色を可能な限り再現しようと研究を続けています。斉彬が思いを込めて推進した薩摩切子を、いかにして現代に蘇らせるか。復興開始から約30年。その歩みは今も止まりません。

鮮やかな色を生み出す、溶解窯がある工房
薩摩びーどろ工芸では、生地となるクリスタルガラスの製造から手がけます。窯があるからこそ、新しい色ガラスや新しい製品の開発にも積極的に取り組めます。手仕事であることを活かし、1点物のオーダーを受けることも少なくありません。
ガラスを溶かす溶解窯は1年中休みなく火が絶えることなく、1300~1500度でガラスを熱し続けます。溶けたガラスを吹き竿の先にとり、金型に色ガラスを吹き込んだ後、透明ガラスを押し込んで密着させます。

膨張率や収縮率が異なれば、破損にもつながります。色の出方も異なるので、ガラスの温度や状態を見極めることが、職人技。
さらに、色ガラスと透明ガラスの厚みを一定にし、重厚感がありながら、厚すぎず、薄すぎないガラスの器を生み出すのも、薩摩びーどろ工芸の職人ならではの技術です。
ちょっとしたタイミングや温度変化を見誤るとガラスの破損にもつながるため、繊細な技術が求められます。それに応えるべく、職人たちは日々、技術を磨きつづけています。
ガラスと語り、ガラスを見極めながら、一点のガラス器を吹き出す。その美しさが最大限に引き出されるように、慎重にカットしていきます。その組み合わせから生み出される薩摩切子だからこそ、大切な人にふさわしい贈り物にぴったりです。
Buyer’s Voice 代表・松澤斉之より
重厚感と柔軟性。ガラス生地から作るからこそできる美しい切子
江戸切子と並べるなら、薩摩切子。そう思って薩摩びーどろ工芸を訪れ、その製法を見たとき、これは同じ「切子」とひとくくりにできるものではない、と感じました。
自分が男性だからなのか、江戸切子と比較して厚みがある重たい質感は、手にしっくりきました。
鮮やかな発色、ツヤ感も、薩摩切子ならではの良さだと思います。伝統を復元したとはいえ、新しい色への挑戦やカット技術の開発などにも、積極的に取り組んでいます。
驚いたのは、上下に異なる色ガラスを被せた2色の薩摩切子。他にはない、薩摩びーどろ工芸ならではの技術で、歴史を受け継ぎながら、新たな薩摩切子の世界を作り上げようとしています。
薩摩切子復元から30年。職人たちはまだ若いです。今後、柔軟な発送から生まれる新たなチャレンジで、どんな切子が生まれてくるのか、楽しみでもあります。
*天然光で撮影したいくつかのグラスを掲載していますので色味をご確認ください。