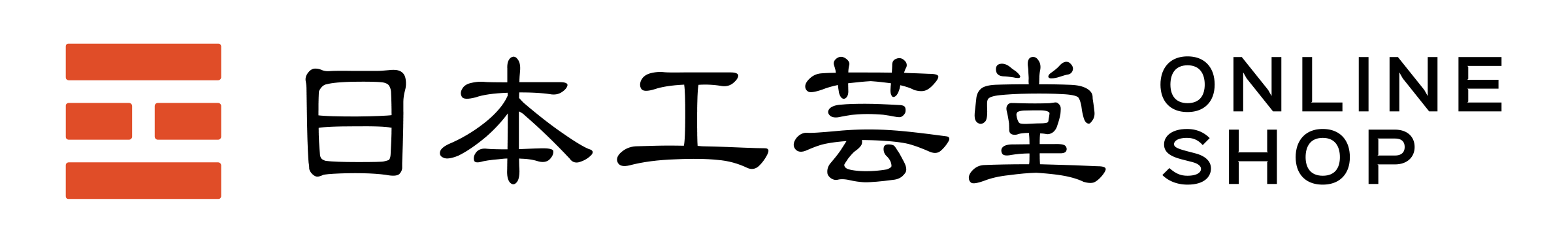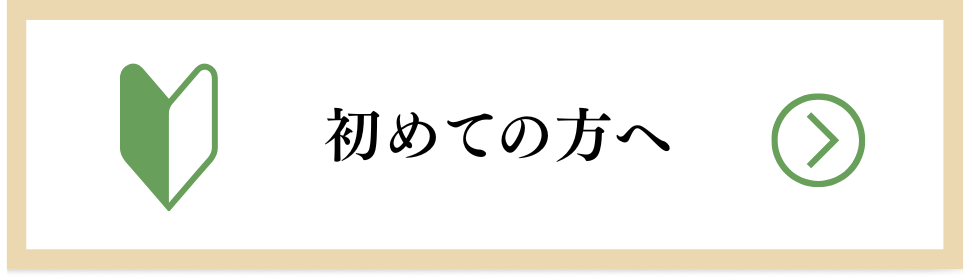創業にまつわる3つのエピソード

想いをつなぐ、工芸専門ショップ、日本工芸堂が重視していることは、工芸品の背景にある「物語」を伝えること。作り手や産地の想い、歴史を伝えていくことで、伝統工芸の魅力を深く感じてもらうということです。そんな想いを抱くきっかけになった創業前の3つのエピソードを記載してみようと思います。
1.「産地に誇りを」~旭川での話
日本工芸堂を始める前、私(代表、松澤)はAmazonのホームカテゴリーのバイヤーとして多くの産地を回っていました。ホームカテゴリーとは家の中にある電源の使わない品々を扱う事業部で、Amazonで販売可能な商材を発掘して流通させることがミッションでした。
そのとき、北海道の旭川に行っていました。旭川は日本五大家具産地にも数えられる産地。大雪山系の森の木を使い一世紀以上に渡って作られてきた家具は、手仕事による精巧なものづくりの技が活きる、世界でも高い評価を受けている優れた家具です。自分たちにとって、旭川と言えば家具。「優れた家具をAmazonで売りましょう。全国に、世界に売っていきましょう」。そんな話をメーカーの皆さんにするために、何度か通っているときでした。
その日、メーカーさんへの説明会を終えた後、同行していたバイヤーと一緒に、地元の有名店である松尾ジンギスカンに食事に行きました。隣には、地元の人らしき若者のグループがいました。彼らは気さくに「どこから来たんですか?」と話しかけてきました。
「東京から、わざわざこんなところに何をしに来たんですか?」
そんな問いに「旭川の特産品を買い付けに来た」と答えました。それに対し彼らは言いました。
「特産品?なんだろう。ラーメンですか?」
驚きました。旭川に生まれ、育ったのであろう若者たちは、旭川家具を知らなかったのです。
天然木を使った旭川家具。職人さんが丁寧に作っている北海道の銘品。私たちが魅力を感じて産地を訪れ、生産現場を見せてもらうことでその魅力をより強く感じていたにも関わらず、彼らはそれを知らない。”旭川家具”だと伝えると
「そういえば、友達の親がそんな仕事をしていた気がする」
と答えるほどに。
伝統工芸が廃れていく一因を見たような気がしました。思い返せば、他の産地に行ったときも、その地域の産品に対する誇りを地域の人が十分に感じているかと言われればそうではなかったように思います。自分の住む地域で作られているもの、ひいては自分の国で作られているものに対して興味と敬意を持ち、自国の歴史に根付く文化を誇れるような、そんな取組みが必要なのではないか。そう強く感じました。
そのために何ができるんだろうか。私は少しずつ、そう思うようになりました。

2.「作る人の話を聞き、現場を体感するからこそ」~瀬戸での話
さまざまな産地に行くときには、食器を専門に卸している会社の方と伺うこともあります。すでに取引がある方を通じて行くことで、産地訪問もスムーズになるからです。
20年に渡り百貨店などに食器を卸している会社のAさんとは、一緒にさまざまな産地に行って、Amazonなどオンラインでの販売方法などを説明していました。あるとき、Aさんはふと思いついたように言いました。
「松澤さんは本当にいろいろな産地に行ってますよね。百貨店のバイヤーよりずっと多いですし、ここ3年の現地入りの数は、私の20年より多いと思いますよ」
驚きました。卸売の営業をやっているAさんは、現地に行って産地を見て、商品を見て取引を決めるのが仕事だと思っていました。でも違うのです。地域に行かずとも、東京にいれば、産地から商品は送られてくる。どんな商品なのか、どんな価値があってどのくらいの値段で売るものなのか。その種の資料を見て、売れるものなのか、そうでないのか、どんな場所なら売れるのかを判断する。それが卸売のバイヤーの仕事になっていたのです。
オンラインで商品を販売するのは、その最たるものかもしれないです。産地で見てきた製造工程や素材などの付加価値ある情報を削ぎ落とした表現になってしまっている、と。値段や色、形、サイズなど、数字や写真など目に見えるものの方が分かりやすいからと見えづらい情報は記載されません。その製品の背景にある歴史や文化、素材の特徴、職人の想いなどは伝えられていないことに気付いたのです。
ここに大きなギャップがあると感じました。そして、作っている職人さんが皆さん直接その魅力を伝えることは難しいかもしれないが、現場で感じたことを伝えることは今後、お客様に求められていくんじゃないかと。なぜなら、産地を見て、職人さんの話を聞くことを私はとても面白いと感じていたし、知ることでより魅力は深くなり、それが付加価値になっていると思ったからです。
このプロセスは、当時の商流では絶対的に足りていないものでした。自分が感じたことを、オンラインや何らかの形で伝えるために試行錯誤していくことは、とてもやりがいがあることなのではないかと思い至りました。
>工房訪問一覧:つくり手に会いに行く
3.「顔の見えない流通から顔の見える流通へ」~津軽での話
私は酒器が大好きです。伝統工芸の技で作られる酒器には特に魅力を感じるような気がします。
そのときに訪れていたのは青森で、津軽びいどろの工房を見せてもらっていました。吹いている現場も見せてもらったし、実際に宙吹きでグラスを作る体験もさせてもらいました。毎回同じ形のグラスを宙吹きで作る職人技のすごさも感じていました。

楽しく現場を見せてもらった後、津軽びいどろを作る会社の方や流通を担当する方などと食事をすることになりました。津軽びいどろのグラスも持ち込まれ、津軽三味線を聞きながらの宴会はとても楽しいものでした。鮮やかな色ガラスがちりばめられた酒器を、心から「いいな」と思いました。だからふと聞いてみたのです。
「この酒器を使って東京でお酒が飲める場所を教えてください!」
その場には、津軽びいどろを作る人、流通させている人、みんな揃っていました。ですが、誰も、どこで津軽びいどろが使われているか、答えることができませんでした。
「顔の見えない流通」がそこにあることに気付いた瞬間でした。
野菜であれば、売り場に生産者の名前や顔写真があり、それが信頼につながっています。ときには生産者が売り場に立ち、実際に消費者と言葉を交わしながら販売する市場やマルシェが行われることもあります。「顔が見える」ことは信頼につながり、付加価値になるはずです。
工芸品にはそれがなかった。自分を含めて流通に携わっている人は作っている人を知らず、使っている人を知らない。当然、消費者は誰がどんな気持ちで作っているものなのかを知る手段がなかったのです。
食べ物でなくても、作り手が見えることは付加価値になるはずです。携わる人がどんな気持ちで作っているのか、どんな素材を使って、どんな苦労をしているのかが分かれば、興味も湧くし魅力を感じてくれるはずです。なのに、お客様に近づくほどにそんな重要な情報は抜け落ちてしまって、モノだけがそこにある状況になっていることに気付きました。
だから、伝統工芸品は、その付加価値を価格に十分に転嫁できていないのだ、と気づきました。それこそが、日本の伝統工芸が少しずつ廃れていく一因になっているのではないか、と。

津軽びいどろ@青森、北洋硝子にて2016年春
まとめ
こうして私は、日本の伝統工芸の生産者や産地と、それを求めるお客様との間を結び、生産者と産地の想いをメッセージとして届けていくことを仕事にしようと決めました。
多くの産地で感銘を受けたこと、感じたことを伝えることは、多くのお客様にも強く求められているだろうという仮説です。私が感じたことに興味を持ち、伝統工芸に関心を持つ人はきっと少なくないだろうと思いました。
そんな人に、正しく魅力を伝え、価値をきちんと届けていくことは、非常に重要なんじゃないかと、今も思っています。
お客様の心に、私たちが産地で感じたことを直接お伝えし、お客様から頂いた言葉を産地にもきちんと伝えていく。産地からお客さまの手元まで、その魅力や価値を正しくつなげていくことはとても意味があるし、面白い。
3つのエピソードから生まれたそんな想いを胸に、私たちは日本の伝統工芸をより多くの人に伝え、産地を支えていく活動を進めていきたいと思っています。
日本工芸堂、松澤